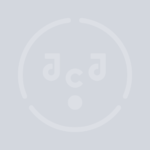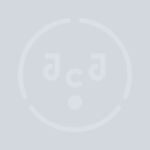その日の朝、強い冬型の気圧配置によって北日本の日本海側は吹雪に見舞われていた。秋田市にも風雪注意報が発表されていたようで、ベッドから起きてカーテンを開けると、私は一瞬、自分がどこにいるのかを見失った。窓ガラスを一枚隔てた空中では無数の雪片が乱舞し、その先には白い闇が果てしなく広がり、都市の形はホワイトアウトによってもはや識別不能になっていた。
私が住むのは再開発が進む秋田駅前地区の高層マンションの一室である。雪が積もることなどほとんどない横浜市から引っ越してきたばかりの私にとって、その光景は思わず声を上げてしまうほど衝撃的だった。いつもは朝から耳障りな騒音とともにはじまる近隣の建設作業も、吹雪の影響で凍結されたのだろうか。見下ろす工事現場は雪に覆われ誰もおらず、ひっそりと鎮まりかえっていた。
マルク・オジェは、資本によってルーツやアイデンティティに根差した「場所」が失われ、現代の至る所で生み出される均質化した空間や景色を指して「非-場所」と言った。秋田公立美術大学大学院発刊の広報誌『TRANS01』(https://www.akibi.ac.jp/daigakuin/news/trans01/)のなかで私は、秋田の地が重要無形民俗文化財の宝庫であることと、近現代における身体表現分野の先駆者たちを輩出してきたこととの間に、秋田特有の風土を介した関連性を見出し、「秋田とは地図上の地域区分のことではなく、私たちの身体感覚をつなげるひとつの内部空間なのだ」と述べたが、そんな秋田ですらオジェの言う「非-場所」化から無縁でいられないということは、駅前地区の再開発を見れば明らかである。
しかし面白いことに、黒いアスファルトが雪面で覆われ、風雪によってイオンやユニクロの看板が掻き消され、都市のおよそすべてが白い闇に侵蝕されながら抽象化されるとき、資本によって「非-場所」化されたはずの都市は、ちょうどマイナスにマイナスをかけるとプラスへと極性が転じるように、二重に「非-場所化」されることで再度「場所」へと反転する。ただしそれはオジェが言う具体的な歴史やアイデンティティへと根ざした「場所」ではない。その「場所」はむしろそれらから断絶され、場所を場所として認識しようとする意識が遭難させられることではじめて還ることができる、極度に抽象化された「場所」である。一切のトポロジーを超えたその「場所」の只中で地図は意味を成さない。さらに時制も失われ、時間が滞留して感じられるが故に、それはどこか懐かしい故郷のようにも感じられる。私たちはそのなかに身を縮こませて閉じこもり、同時に自らの身体地図を手がかりにあらゆる場所へと開かれていくのである。
そうやってしばらく窓の外に広がる白い闇に意識を奪われていた私は、ふと我に返った。そして自宅から3キロメートル離れたBIYONG POINTで開催されている宮本一行の個展『雪面の歩行 Walk on the Snow Field』を、自らの足で歩いて再訪してみようと思い立ったのだ。
ホワイトアウトの中で人間は方向感覚も、平衡感覚も、距離感覚も奪われるという。札幌近郊ではホワイトアウトで家を見失った人が、自宅からわずか数十センチ手前で亡くなっているのが発見されたこともあるらしいが、中通り、竿燈大通り、山王大通りとほぼ一直線に歩けば、多少視界が悪くても問題なくここからBIYONG POINTへは辿り着けるはずだ。私はボーナスをはたいて買ったばかりのダウンジャケットに身を包み、暖房の効いた家から外へ出て、1時間弱の旅へと繰り出した。
北国の人には笑われるかもしれないが、私は秋田に来るまでダウンジャケットのフードを飾りとしてしか考えたことがなかった。「シェルジャケット」とはよく言ったもので、荒々しい風雪に襲われる環境下で、それは生存のための外殻として機能する。しかし毛皮を持たないヒトのような動物が、よくこんな環境で生きてこられたものだな…などとえらく感心しながら、私は黙々と風雪のなかを歩いた。息を吸うたびに肺に冷気が流入し、逆に息を吐くたびに肺からの呼気が蒸気に変わって身辺に拡散される。周りの状況を視認することは難しい。しかし環境からの数多の刺激によって己の身体が「いまここ」に在る、ということだけは強烈に感じられる。私は一歩、また一歩と足を運び、ブーツの靴底で雪をぎゅうぎゅうと踏みしめながら会場を目指した。足への体重の掛け方や、足の運び方次第で雪を踏みしめる音はさまざまに変化する。降り積もった雪の感触を確かめながら、その変化に耳を澄ますことはなかなかに愉しい。
しかしこうして歩きながら考えてみると、そもそも身体には能動と受動の区別などないということがよくわかる。私自身もその一人だが、演奏家と呼ばれる人たちは己の身体地図があらゆる場所と地続きになっており、自分がその相互作用の狭間で生きているということを体感的によく知っている。例えばドラマーがドラムを演奏しようとするとき、一見それは能動的にドラムを叩こうとしているようでいて、実際にはそうではない。その時ドラマーはスティックを介して自らの手へと伝わる反射をその都度、受動的に感覚しながら、スティックの握り方をはじめ、あらゆる身体の構えを微妙に調整し、さらにドラムそのものや、その音が響く空間そのものとも絶妙に呼応しあいながら、打面から最適な音を現象として「引き出して」いるのだ。もし歩行する際の私の足がこのドラマーの手で、地面や床面がドラムの打面だとするならば、自宅や職場であろうと、あるいはアスファルトや雪面の上であろうと、自らが踏む地面や床面から、同じように音楽的な現象を引き出すことは十分可能である。たとえそれが音として聴こえなくとも、常に己の足もとで身体と世界との間に豊かな交感が生じているということは、いくらでも感じ取ることができるはずだ。

どれくらい時間が経っただろうか。そんな由無し事を考えながら黙々と雪面を歩いているうちに、前方に霞んだBIYONG POINTが見えてきた。なんとか目的地に辿り着いた私は、自動扉を抜けて建物に入った。中はむんむんと暖房が効いていて、身体に付着した雪はたちどころに溶けて水滴に変わった。私は息絶え絶えになりながらダウンジャケットを脱ぎ捨てて、少々乱暴な手つきでロビーの芳名帳に名前を記し、呼吸を整えてから展示室のなかへと目をやった。
BIYONG POINTの展示室はとにかく白い。思えばBIYONG POINTほど完膚なきまでのホワイトキューブを私は知らない。建物の入り口に貼られた数々の観光ポスターとは裏腹に、その空間にどこか秋田的なルーツやアイデンティティを漂白せんとする意思を感じるのは私だけだろうか。壁面はおろか、床面から天井に至るまで執拗に白で覆われたその幾何学的空間は、まさにオジェの言う「非-場所」である。
これまで宮本は自らの身体的行為を手がかりに、サイトスペシフィックな「場所」との対話を志向してきた。一方本作において宮本は、このBIYONG POINTのホワイトキューブを展示のための空間というよりも、作品の素材として積極的に活用しながら、むしろ「非-場所」との対話を志向しているように思われる。確かに宮本が歩いたのが、北海道中央部に位置する「大雪山」であることは情報として示されているし、展示室の外ではその具体的な記録映像が流されてはいるが、本質的にはその雪山も「非-場所」として扱われていると言えるだろう。なぜなら宮本が歩いた大雪山のことを、アイヌの人々は「カムイミンタㇻ(神々が遊ぶ庭)」と呼んできたが、和人である宮本がどんなにその山の雪面を踏みしめようと、その足が山のルーツやアイデンティティに根ざすことはないからだ。北海道の開拓が日本における「非-場所」化の先駆であり、「大雪山」という名称も近代になって和人によって名付けられたことを思い出してみても、宮本が歩いたのは「カムイミンタㇻ」という「場所」ではなく、最近になって「大雪山」と呼ばれるようになった「非-場所」であると言うべきだろう。
『雪面の歩行 Walk on the Snow Field』でまず特筆すべきは、この「非-場所」性、あるいは「ノン-サイト」性にある。この「ノン-サイト」というキーワードにロバート・スミッソンを連想する人も多いだろう。あるいは宮本の提示する「歩行」というキーワードから、リチャード・ロングを想う人もいるかも知れない。しかしこれらランド・アートの先駆者たちは、それを志しながら「サイト/ノン-サイト」の二元論をついぞ解体することはできなかった。対して『雪面の歩行 Walk on the Snow Field』での宮本は、ランド・アートの先駆者たちと同様に、ある土地へフィジカルには強くコミットしながらも、まるで音というものが発音された瞬間に消えていくその宿命に倣うかのように、自らの作品から「場所」を消し去ろうとする。そしてその刹那的態度によって「サイト/ノン-サイト」の二元論を乗り越えているように思われる。
だから宮本は現場で採集した「場所」の断片を展示室に持ち込んで、素材として利用するという常套手段を使わない。展示室にはただ宮本の足が雪面を踏みしめて歩く際に生じたノイズと、その身体に装着されていたカメラのブレの、アウラ無き複製が集積しているだけである。一定のテンポで踏みしめられる雪面のノイズは分節化され、8枚の床板に設置されたアクチュエーターへと伝送されている。それぞれの床板を介してバラバラに再生される一歩一歩のノイズは、空間で互いに干渉しあうことでリズムの輪郭を失い、モワレになって霞み、さらにはBIYONG POINTのホワイトキューブが生み出す残響も相まって、茫々たるホワイトノイズと化して観客を待っている。

ロビーでブーツを脱いで展示室へと入り、床面に設置された床板に足を乗せ、ゆっくりと体重をかけていくと、いわゆるベンド奏法の要領で板の固有振動数が高くなり、そこに響くノイズにバンドパス・フィルターをかけたかのような音響変化が現れる。ここで注目すべきは、この効果がセンサー等を用いてエフェクターを制御するような作為的な仕掛けによるものではなく、完全にアコースティックな現象によって生じているという点だ。その微細な現象に耳を澄まし、意識を集中させるとき、観客は自らの内に「場所」を発見することになる。なぜか。それはたとえ元となる音源、つまり宮本が雪面を踏みしめるノイズがアウラ無き複製であったとしても、その現象自体は観客の身体の関与によって純然たる物理法則として「いまここ」で引き起こされているからだ。つまりそこでまず聴取すべきは宮本があらかじめ用意した音の方ではない。私たちが存在し、そこに関与することで絶えず変動している世界の響きの方なのだ。こうして観客が己の「いまここ」から、その「場所」へと至ることによって、宮本がかつて歩いた雪面は、観客自身の身体地図と地続きになっていく。そして「いまここ」に在る観客の身体と、かつて在った宮本の身体との間に時空を超えたアンサンブルが生まれ、その交感に意識的であればあるほど鑑賞体験もまた深化していくのである。
宮本は自らの作品と観客とが相互に関わりあうことによって生じるこのような微細な現象を、ひとりひとりの実存に関わる大きな問題として、何処まで真剣に受け取れるかを問うている。世界に関与しようとする身体が在る限り、そしてそのことを感じ取ろうとする感覚がある限り、この世には「場所」しか存在しない。どこにも「非-場所」や「ノン-サイト」などというものは存在しないのだ。宮本の『雪面の歩行 Walk on the Snow Field』は、そのことを静かに私たちに語りかけている。
作品撮影:船山哲郎
Profile プロフィール
Information
宮本一行 個展「雪面の歩行 Walk on the Snow Field」
※展覧会は終了しました。
▼ 宮本一行 個展「雪面の歩行 Walk on the Snow Field」DM(PDF)
■会期:2023年9月16日(土)〜2023年12月25日(月)
入場無料、無休
■会場:秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINT
(秋田市八橋南1-1-3 CNA秋田ケーブルテレビ社屋内)
■時間:9:00〜17:30
■主催:秋田公立美術大学
■協力:CNA秋田ケーブルテレビ、秋田プライウッド株式会社
■制作協力:NPO法人アーツセンターあきた
■お問い合わせ:NPO法人アーツセンターあきた
TEL.018-888-8137 E-mail bp@artscenter-akita.jp