秋田公立美術大学サテライトセンターにて3月に開催した安村卓士の個展「ずるずる構築体(展覧会)」(2024年3月8日〜3月31日)。会期前半の3月11日には安村が尊敬するふたりの作家を招いてトークイベントを開催しました。
そのふたりとは、大型の彫刻作品やパフォーマンス、映像、インスタレーションなど多様な表現を展開し世界的に活躍する曽根裕氏と、ジャンルや素材にこだわらない美術表現を各地で実践してきた藤氏。安村が最も話を聞きたかったという、ふたりの対談の模様をアーカイブします。
ドローイングをしながら語る、「作り続けること」「方法を発明すること」
「おもちゃ作品」を制作する安村が「作り続けること」「方法を発明すること」をテーマにふたりに聞きたいこととは…
・物語について
・ツールとしての作品について
・公共について
・作品に含まれる作品以外のこと
・コラボレーションについて
・変身すること
・自己批評性
・素材について などなど
プロジェクトを考え、方法を発明し、さまざまな表現活動を展開するふたりの巨匠を前に、安村はたくさんの質問を用意しました。会場には画材やおもちゃ、書籍等が並び、後ろの壁にはキャンバスが貼られています。テーブルに置いたアクリルボックスに「聞きたいこと」の紙が入れてあり、ふたりがくじ引きのように紙を引いて質問に答えるスタイルです。
「すごくレアな機会をいただいて緊張しています」と話し始めた安村は、自分が制作していくなかで「今後も影響を受け続けるであろう」という尊敬するふたりを紹介しながら、自己紹介のドローイングへと促します。「おふたりに自己紹介のドローイングをしていただいて、そのあと箱の中に50個ぐらい質問があるので、引いてもらって答えていただけたらと思っています。あとは好きにしゃべっていただけたら……」
箱の中から最初に引いたのは「形式を発明すること」でした。「藤さんも曽根さんも、いわゆるアートっぽいものとは別の独自の形式を生み出していて。それは一体どういうふうに生み出していったのかが気になっています」と安村。ふたりは考えつつ、はぐらかしつつ、いつの間にか「お題が書かれた紙を貼る」という形式を作り、次のお題「崇高さ」へと移りました。

「あまり考えていないですね」という藤に対し、「崇高さを狙っちゃいけないでしょう。毎日歯を磨くとか、そういうことだと思う」と曽根。
安村|藤さんがいつも話されているカエルは、本当はウサギなんだよ、という話があって。それは崇高さの話にも繋がるような気がして。場所によって変化する、そういう意味でのカエルなんじゃないかなと思っていて。
曽根|跳ねるの、好きなの?
藤|そう、跳躍。常識や今の状態から越えることだから。単純にケロちゃんが好きだったというのもある。
家族の存在と、生きること。死ぬこと
ふたりのトークは、脱線しながら行きつ戻りつ、分かる人には分かる内容でゆるゆると進んでいきます。次のお題は「家族」。ふたりにとって、家族とはどんな存在なのでしょうか。
曽根|これ重要。家族がいなかったら死んでいるよね。作り続けることができているのは、パートナーや家族が許してくれているからというのがある。生かしてくれている。
曽根がおもむろに大きく、描くように書いたのは「死」という文字。しかしそのあと、「死」を「生」に変えました。
安村|藤さんの場合、作品が生まれるところは日常であったり家族の関係であったりしますよね。そこからどうやって作っていくのでしょうか。
藤|僕は、親には反発しかしていなくて、死ぬまで話ができなかった。ただ父母とも僕を束縛はしなかった。父親は、僕ががまくんとかえるくんの紙芝居をひとりで全力でやっているのを見て、大学院まで出たのにと泣いていたけれど。学生時代に僕は、母親にひどいことを言ったことがあった。『おまえが生きているから自分は自由にできない』って。今は家族の問題をどうにかするためにカフェを経営したり、ゴミを集めたり。妻の活動にただ付き合っているだけというのもある。
次は、「コラボレーション」について。
藤|昔はそういう概念がなかったから、コラボレーションとかコレクティブといった言葉が出てきた時にいいなと思った。1970年代は〈グループ〉としてリーダーがいて、主張があったけれど、それぞれが対等な関係というのがあっていいと思っていた。20代の頃は自分の作品だけで空間を仕上げたことはなくて、ほとんどは誰かとのコラボ。他の人の作品を入れて、あえてずらしたかった。
曽根|ひとりでやる空間って、ほとんどないよね。展覧会にはそもそもキュレーターがいるから、もともと誰かとの共同の作業ではある。僕の場合は、特に職人さん。アートというより、技能。
「制作する欲望」というお題には、「欲望ってあるのかな」と曽根。
曽根|欲望はしないけれど、没入はする。食べて寝て、作りたくなる。疲れて寝て、また作りたくなる。それがずっと続くのかと思っていると少しずつ変わってきたりして。
藤|僕は、没頭していたい。僕の場合、時間の質を変えたくて何かを設定しているところがある。犬を100匹作るとか。何も考えずにそういう毎日に没頭していたい。制作する時間が心地いいんだよね。
曽根|心地いいし、つくりたいという欲があるからね、純粋に。
「具象と抽象」のお題では、「僕の考えでは、両方とも抽象です」と曽根は断言しました。
曽根|写生をしている時であっても、何か抽象の作業をしているもの。具象と抽象は対になれない言葉。
藤|具象と抽象はレイヤーが違う。並べてしまうのは美術に冒されているのかも。具体と抽象なら分かるけれど。
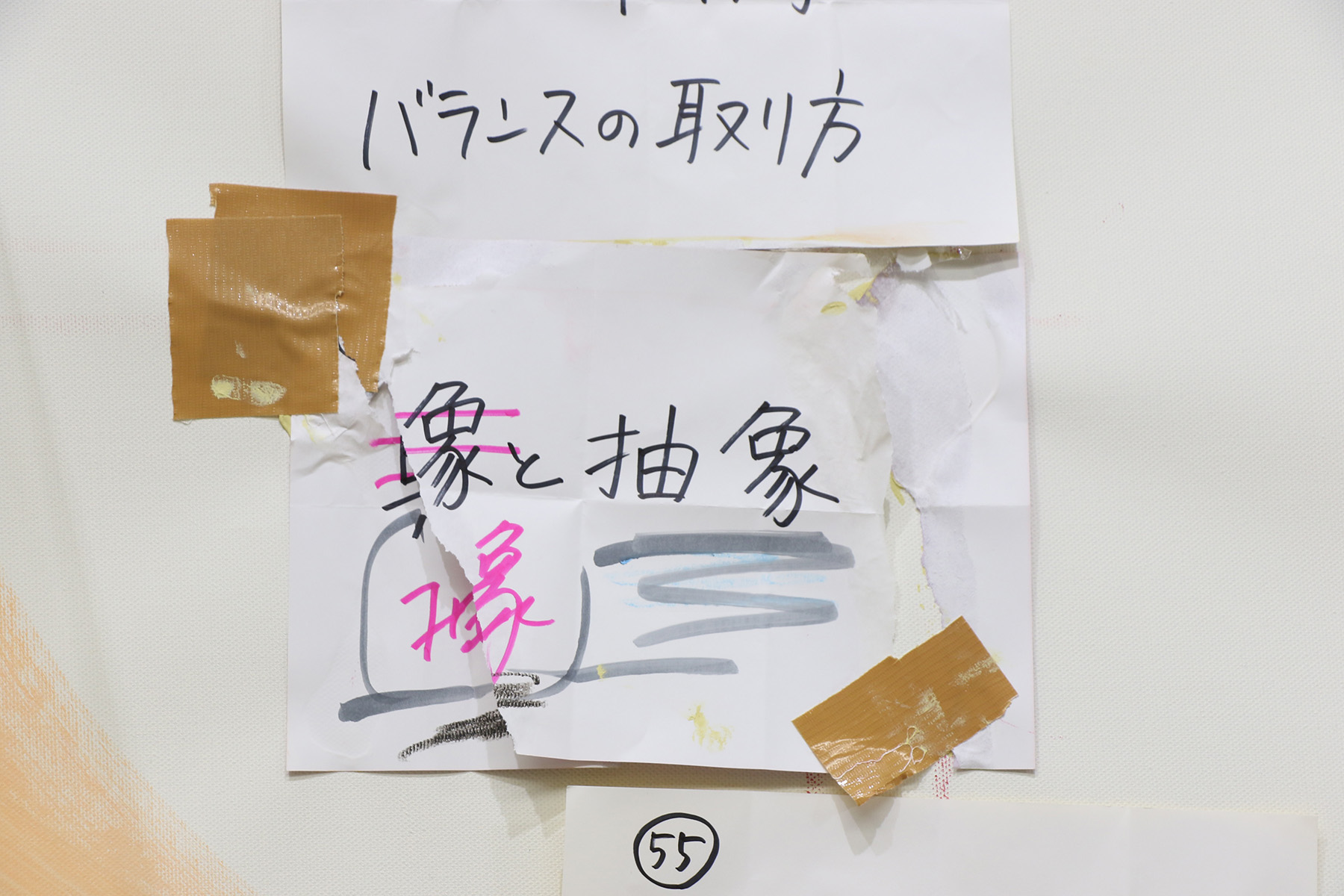
安村|例えば藤さんのトイザウルスは、具体的なトイザウルスというイメージがあるけれどそれ以前におもちゃが集まってくるシステムがある。僕たちは目の前にトイザウルスという具体的なものを見てはいるけれど、それがほどけていくような感覚。具体的なイメージを作ることと、システムが背景にあることはどのように関連しているのか聞いてみたいなと。
藤|僕が滞在していたパプアニューギニアではフェイスペインティングなど言語化されたり文字化される以前のものがあって、それが表記の方法だった。鳥になったりワニに近づこうとしたり何かに変容するためのもので、図柄は抽象的だけれど具体的なアプローチがあった。僕の場合、そういうことを経由しているのは大きいだろうと思う。
次は、「動的平衡」について。
安村|藤さんの本棚に『動的平衡』という本があって、それが藤さんにぴったりくるなという印象がありまして。さっき話されたように自分ひとりじゃなくて他の人も含めて展示をつくるとか、自分をずらすとか。藤さんは動かしながらバランスをとっているんだなと。
藤|俯瞰している感じはあるかもしれないね、どこか冷めている。制作し続けて動き続けなければいけない感覚はある。止まるとおしまいみたいに。なぜ動くのかというよりも、そうせざるを得ない感覚があるね。
「展示以外の場」では、ふたりの出会いの話になりました。
藤|展示といっても、結果的に展示することもあるけれど展示しないことも多いよね。曽根さんとは1995年にタイで開催されたチェンマイソーシャルインスタレーションにお互い出品していて。オープニングをやって、みんな展示したんだけれど、その時、曽根さんは山を歩いていた。人に旅をさせる映像を出して、自分は山を歩いていたんだよね。
曽根|子どものためにご飯作らないといけなくて。だから他の人に代わりに旅してくださいって。
藤|僕は同じ時にチェンマイの街中を1カ月歩き続けていて、トレーシングペーパーに書いてためるだけためたけれど、結局展示していないんです。だから当時、ふたりはまだ会っていなくて。
「公共」というお題では、なにやら話しづらい雰囲気に。
藤|パブリックアートに対して、1991年にプライベートアートをやったことがあって。当時、僕が東京の廃墟ビルに借りていたスタジオを、1日1組がプライベートな時間に使う状況を作ったことがある。その頃はパブリックアートって何? パブリックって何? みたいなことがあって。パブリックアートのひとつの方向性として、1989年から1996年に鹿児島で親と一緒にカフェをやったんです。パブリックとは、「どうひらくか」「誰とシェアするか」ということなのかな。根底にあるのはパブリックアートへの違和感だよね。街中に立っているパブリックアートといわれるものに対して、当時は『違うよね』という言い方をしていた。

価値とは、関係のなかからしか生まれない
「お題が書かれた紙を貼る」という形式から変えようとするふたり。ふたりの話はうまく噛み合っていないような、いえ、うまく呼応し合っているようにも見えます。このあと、「価値を変えること」「純粋さについて」「作品を残すこと」などのお題を行ったり来たりしながら話が進みました。
曽根|純粋さというのは、作品を残すことに繋がると思う。何に対して純粋なのかというのはあるけれど。でも作品を残さない純粋さというのもあって、両義的だね。世のなか物質が氾濫していて我々はそこから逃れられないんだけれど、マテリアリズムからの構造として「作品を残さない」ということが純粋であるという考え方もあっていいと思う。
藤|価値というのは明らかに関係のなかでしか生まれてこないと思う。状況や関係によって価値が変わる、価値を変える。変えるには関係を変えていく。僕はその関係をどう作っていくのかにシフトした時期があって、ワークショップの手法をとって意図的に関係を作っていくことをしていたんだけれど、だんだんつまらなくなって、ものを作りたくなっていった。
曽根|揺れるんだよね。
藤|そう。ものを作ることに興味がなくなった時期に“かえっこ”などの〈仕組み〉が作品だと思ったけれど、でもやっぱりものを作らせてよ、と思うようになった。それは時間の話でもあって。制作する欲望というよりも、作っている時間が好きだからというのがあるよね。
曽根|アートよりも人間の進化のほうが速いんじゃないの?と思う。人間はどんどん変化していく。アートのほう先に行っているという錯覚があるけれど、現実世界ははるかに速くて、価値が変わっても変わっても新しいものが出てくる。
ふたりの話は〈切実〉と〈誠実〉の話へ。
曽根|僕は、切実かどうかよりは、自分に対して誠実かどうかが大事。自分に嘘をつくと絶対にバレる。気持ち悪くなるし、すっきりしない。
藤|切実さというのは、やらざるを得ない、やらないとダメみたいな感覚。このトイザウルスは結構、切実なんです。何も捨てないと決めているからね。“かえっこ”でおもちゃがどんどん集まってくるから、どうにかしないといけないんだけれど、捨てないというルールを自ら課している部分があって。父と母との関係もどうにかしなきゃいけなくなって、アート系のいろいろなことが発生するようなカフェを経営することになるのは、当時、切実な問題だった。
「物語」というお題では、作品の構造の話になりました。
曽根|ナラティブは重要ですよ。だいたい僕の作品には、物語という起爆剤がある。概念的なものでしか表現できない物語を一列に並べることをするのは3年に1回ぐらい。物語には階層ができていて、メインの物語とサブの物語がある。メインがあってそれがバレないように違う物語を入れたりする構造。絵の具を重ねていくように、いろいろな物語を何十にも重ねていく。テキストAがあって、それを否定するテキストBをAの後に平気で使ったり。コンセプトとか物質の重さをちょっとずらすの。アルミは合金なんだけれど、アルミと言った場合と合金の種類と言った場合とでは、概念的にも、イメージのスピードも変わると思うんです。指し示している物体は同じなんだけれど、タイトルによって作品を見る目や位置付けが変わるのと同じ。
実はアートってずるくて、タイトルと内容物を捻じ曲げた例はいっぱいある。そのルールみたいなものを積極的に使って、物語を分かろうとすると次の物語が始まって次の作品に続いたり。それを僕は意識的にやっていますね。
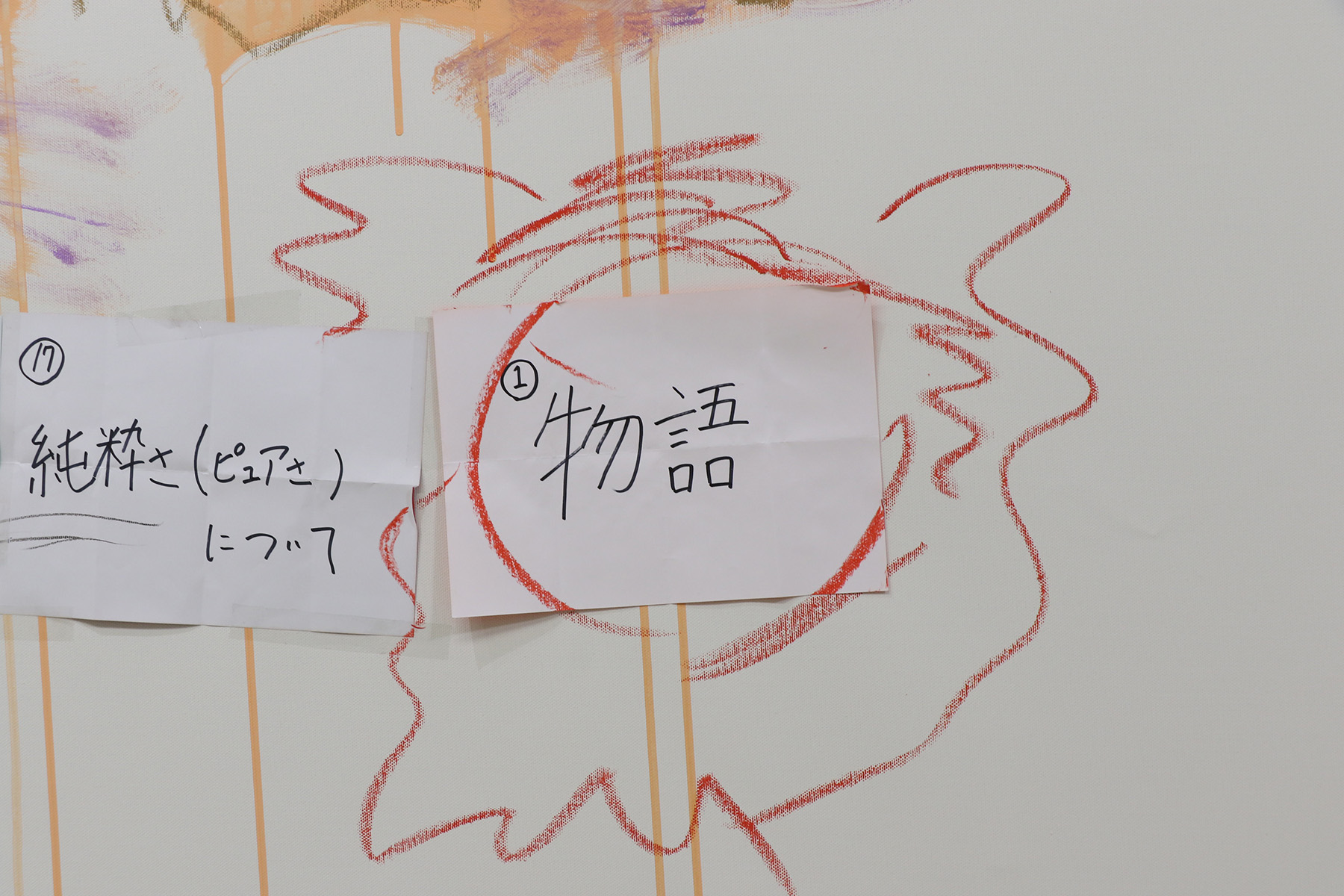
藤|僕の場合は、物語をつくらないんです。影響を受けたアーノルド・ローベルの『がまくんとかえるくん』の話を、大学院を出てすぐ紙芝居にして全力で読むパフォーマンスをしていたんだけれど。そのなかにかえるくんががまくんにお話をしてと頼む話がある。がまくんは何を話そうか逆立ちをしても虫を食べても自分に水をかけても、頭を壁に打ちつけても思いつかなくて倒れてしまった。そこでかえるくんは、では自分が話そうとがまくんに『がまくんは何を話そうか逆立ちをしても虫を食べても自分に水をかけても、頭に壁を打ちつけても思いつきませんでした。具合が悪くなって倒れてしまいました』とう話をした、という話。がまくんはフィクション、かえるくんはドキュメントとして物語ができているという話。
僕は、何かを作ろうとする態度が重要だと思っていて。身近な関係であったり、おもちゃを集めてしまうこと、給料1カ月分を使ってお米を買うこと、蓮の葉の増加の物語だったり、自分の右往左往がそのまま物語になっていくというのをやっていこうかなと思った。冷静に物語化していくために、表現がある。自分が話していることというのは、自分がやっている紆余曲折だし、いろいろな物語を重ねていくこと。原油だったり自分のアレルギーだったりいろいろなリアルな問題を重ねているから複雑になっていって、切実であるし、そこにはいろいろな物語が込められていく。
曽根|作品の内部構造の問題は、楽しいよね。
藤|ストラクチャー(構造)とスキン(表情)というイメージがあって。僕は構造から作っていって、表情が弱い。曽根さんは構造がしっかりしていて表情もいいよね。
崇高さは、届かないところにあるもの
トークを始めて1時間半ほど経ったころから、参加者の質問に答えていきました。内容は、崇高さについて、公共について、作り続けることについて…。脱線しつつも、おふたりの過去と現在、未来を行き来しながら話は広がり続けていきます。
質問者|先ほど『崇高さ』についてのお話があって、おふたりは目指していないということでした。制作において私は崇高さを目指しているつもりなのですが、おふたりは何を目指しているのか、目指さずに日々の積み重ねでできていくものなのか…。
曽根|正直に言うと、崇高さを目指しています。生きていく崇高さもある。どんな時に、どんな作品のどの部分とは言いにくいけれど。ギャーとなっても紙をくしゃくしゃして捨ててしまうのではなく、しょんぼりしながらまた描くタイプ。崇高さって語りにくいぐらいかっこいいわけよ、だから照れちゃったのよ。質問として出てくるのが早すぎて。
藤|僕は言い方が違ったかもしれないけれど、崇高さを目指しちゃうと作れない。でもどこかで目指しているかもしれない。僕はもともと法隆寺の弥勒菩薩や龍安寺の石庭が理想だと思っているから、それをやるには相当やらないと無理だなと分かっている。だから、自分を束縛したり抑圧するものを横に置いておく。
曽根|僕は逆かも。崇高さを忘れないでいて、狙うけれど、できない。また狙うけれど、できない。次の日も狙うけれど、できない。思いながらも、作れない…。
質問者|作品を作り続けていくなかでいいものを目指していくと思うんですけれど、現状を超える概念がないとそれを目指してはいけないのではないかと思っていて。世俗に迎合していくよりも、その価値観ではなく自分のなかの崇高さ、理想を持たないと目指していくのが難しいのではないかと思っています。
曽根|人の真似って、つまらない。芸術の原理って作り出すことなんだけれど、やっぱりまだ作っていないものを作りたいと思うのは、たとえ達成していなくとも僕はそう思い続けるタイプ。できている、できていないじゃなく、心の葛藤の一部にありますよ。
藤|僕は、流通したり流行るものを作れるのなら作っていいと思う。作れないから、作らない。崇高さを目指している間にそれができていくのはいいと思う。崇高さというのは価値の変化と同じで、誰と見るかで変わるんじゃないかな。ひとりではできないから。ひとりで崇高に、というのは、僕は分からない。
質問者|純粋さや誠実さにつながる問題なのではないかと思っています。
藤|純粋さや誠実さは心の問題で、崇高さというのは外からの評価のような気がする。外からどう見えているか。
曽根|崇高さは、届かないところにあるもの。自分からは切り離されているものなんじゃないかな。ハンドリングできないことなのかな。
質問者|束縛と抑圧のお話がありましたが、公共とかシェアとか、開いていくことを重視して制作されていると思います。束縛や抑圧がある公共的な場所で、抑圧があるなかで開いていくことについて、どう思われているのでしょうか。
曽根|公共のなかにあるのはルールだと思う。ルールを守っていれば、抑圧にはぶち当たらない。公共空間といっても場所としてそこにあって、そこには他者とうまくやっていくためのルールがある。ルールが抑圧を与えないような社会があればいいな。
安村|今回は、場所を与えられたなかで作品を展示するにはどうしたらいいんだろうという疑問や違和感はありました。藤さんは場をつくるということから考えたり、曽根さんはプロジェクトをやることから考えたり。場をつくること、状況をつくること。与えられたものではない、別の場所を組み立てていくことについて聞きたいです。

藤|いかに抑圧や束縛を外すかということはやっているつもりです。それこそ、1980年代にホワイトキューブの概念があって、自由にできる空間といわれたが、自由は概念でしかなくて。どんな場にもそこには必ず条例や法律があり、運営管理計画がある。すべて場所というものは個人の部屋の中でさえも、まったく束縛のない空間は見つけにくい。それをどういうふうに外していくのかで、そこに自由な空間ができていくんじゃないかと思った。
いろんな制約があるなかで自分はどこで何をやるのかと思ったときに、経済のシステムの中に組み込まれているような気がして、廃材を使ってみたり、1カ月のお給料でお米を買ってみたり。そういったところから、公共の場を運営することとか、どうやって使いやすいところにしていくのか、どう場をひらいていくのかと向き合ってきた。それは、閉じこもっていては、存在しないことになってしまうから。こもっている間は、なんらかのかたちで外にひらいていかないと、関係をもっていかないと存在しないことになっていまうという恐怖があった。
閉じた空間で作られてきたものが、ひらくことで存在していく。こもって作り続け、発表できないことを知っている人は、こもり続けることの恐怖を知っているはず。閉じこもっている表現したい人たちがどういう場があればリリースできるのか、誰と関係をつくれるのか、どう連鎖していくのかに興味がある。それは、僕自身もこもってしまうほうだから。どう出していくのかが重要かと思うから。だからつくろうとする態度が重要であって、諦めたら終わり。どうにかつくろうとして、どうにかひらこうとして、ひらくときにはいい人たちに来てもらって。束縛を外すことで、何らかのかたちで外と関係を持ち、ひらいていく。関係ができることで、存在していく。
トークの終盤は、アートと社会、アートと公共の話に展開していきました。未来を決めない藤氏と、10年後まで未来が決まっている曽根氏。まったく違うようでいて、捉え方はどこか似ているところもあるおふたり。閉館時間ぎりぎりまで、それぞれの語りが続きました。
曽根|アートとは何であるかの定義に関係する問題でもあるけれど、アートが無いところというのは、戦場であったり、海の底だったり。人間の状態を保って営利をおこなっているところには、たいていアートがあると思う。
藤|理想のアーティストは、僕は一時期、弁護士の中坊公平だと思ったことがある。アートの定義というのは常識を超えて、価値を変えていくことだと思うから。絵を描いているからアートなのではなくて、大谷翔平とかアスリートもアーティストに近い存在だと思う。自分の限界を越えたり、社会の価値を変えたり。現実的ではない現実を超えたものをつくろうと思う態度を持つ人がアーティストなのだと思う。自分が表現することによって社会の概念が変わり、変容していく。
曽根|どんな時代であっても、汚いお金で描いたものであろうとも、いいものはいい。世界を変えていくアートの力というのは日々あって。道徳や倫理の部分が豊かになっていく方向にあれば、戦争をやめさせることもあるかもしれない。
藤|いいものとして残っていくものは、何らかの変容を生み出していくものだと思う。僕は表現の方法は決めていなくて、誰が周りにいるかで方法を変えていく。隣に演劇をやる人がいたから演劇をして、子どもがいたからおもちゃの廃品を集めて、隣に老人とケーキを作る人がいたからカフェをやって。ものではなく、仕掛けを作ることに関心があるから、僕は続けざるを得ない。右往左往しながら、それが作品に繋がっていく。だから、未来を決めない。目標も、未来もない。崇高さもない。
曽根|僕のスタジオではいろんな時間軸の制作が横に並んでいて、10年後にできるものがもう決まっているんです。10年ぐらいでつくる作品とか、5年ぐらいのものとか、3週間ぐらいでつくるもの、この3日でつくるものとかが並んでいて。10年後が、決まっている。朝起きると、フレッシュな頭でドローイングする。そこにはないものを描く。それから、進んでいるプロジェクトを見ていく。ちょいちょいと手を加えていく。そして1日が終わる。そんなガーデニング式。死ななければ、自分の10年先のことが分かっている。そこから次の10年後に何ができるか。そういう10年のスパンで見ていますね。

Profile ゲストプロフィール
Profile ゲストプロフィール
藤浩志 Hiroshi Fuji
Profile 作家プロフィール

安村卓士 Takuji Yasumura
2018年多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業
2022年秋田公立美術大学大学院複合芸術研究科修了
[展覧会歴]
2020年「ふしぎな洞窟」/高円寺グッドマン/東京
「オルタナスオープン展」/オルタナス/秋田
2021年「手つかずの庭」/THE ROOM’s GARDEN/宮城
2022年「いったりきたり/たったりすわったり」/鴨江アートセンター/静岡
2023年「クロスプレイ東松山」/デイサービス楽らく/埼玉
「儀式フェス」/劇場PARA/東京
「ANTIWAR #SP _RIG_2023」/アトリエももさだ/秋田
秋田公立美術大学開学10周年記念展「美大10年」/秋田市文化創造館/秋田
「黄金町秋のバザールKoganecho International Artist’s Network 2023
誰も知らないアーティスト」/黄金町エリアマネジメントセンター/神奈川
「ATAMI ART DRANT2023巡ーVoyage ATAMI」/熱海市内各所/静岡
Information
秋田公立美術大学卒業生シリーズVol.12
「ずるずる構築体(展覧会)安村卓士」
「ずるずる構築体(展覧会)安村卓士」(PDF)
「ずるずる構築体(展覧会)安村卓士」会場MAP(PDF)
■会期:2024年3月8日(金)〜2024年3月31日(日)
入場無料、会期中無休
■会場:秋田公立美術大学サテライトセンター
(秋田市中通2丁目8-1 フォンテAKITA6F)
■時間:10:00〜18:50
■主催:秋田公立美術大学
■企画・制作:NPO法人アーツセンターあきた
■お問い合わせ:
秋田公立美術大学サテライトセンター(NPO法人アーツセンターあきた)
TEL.018-893-6128 E-mail info@artscenter-akita.jp




