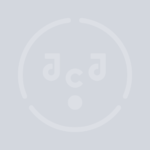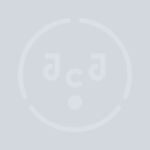特異な制作過程
飯島小雪の作品は、その制作過程そのものがきわめて特異である。未知の相手と交換日記をかわし、そこで生じたコミュニケーションを肖像画として可視化する。私は過去に雑誌『美術手帖』誌上で、現代美術の代表的作家20名近くについて、インタビュー取材と作家論を連載していたことがある。鑑賞者とのインタラクションを作品に取り込んだ作家は複数存在するし、近年でも渡辺篤の「アイムヒアプロジェクト」などが良く知られている。しかし、自身と他者とのコミュニケーションをそのまま作品制作に活かすような手法については、すぐに前例を思いつくことができない。ひょっとすると飯島は、従来にないきわめて斬新な制作スタイルを開発しつつあるのかもしれない。
それにしても不可解なのは、飯島が関係性をどのように肖像画という画像に定着させているのか、そのプロセスである。飯島自身の説明を引用するなら「メディアの移し替えにより意味を強調させる仕組み」1とのことである。ここから直ちに連想されるのはデュシャンの《泉》であるが、広告をアートに変換したウォーホルや、「キャラ」をアートに導入した村上隆など、そうした先例は枚挙に暇が無い。むしろこうした手法を用いていない作家を思いつくのが難しいほどである。
「場所」と「遅延」
ならば飯島の特異性はどこにあるのか。第一には「交換日記」というアナログメディアへの注目である。いまや他者からの「集合的承認」をかき集めるためのモノローグメディアと化したSNSではなく、あくまでも1対1で互いのモノローグを交換するためのメディア。その特異性とは例えば、飯島も注目する「対等性」であり2、「筆跡」をはじめとする非言語的な要素であり、さらに言えば「遅延(時間差)」であろう。私はアナログメディアの最大の強味は、こうした「遅延の強制性」にあると考えている。
交換日記について言えば、それを記してから相手に郵送し、相手がそれを開封して読むまでの時間が「遅延」に当たる。交換日記によって生ずる「関係性」において、おそらくこの遅延が決定的に重要な要素となっている。
私は精神科医として、オープンダイアローグと呼ばれる対話実践の普及啓発に取り組んでいる。対話そのものは相互性があり即時的なコミュニケーションと考えられるが、対話から変化が生まれ、関係性が生ずるのは、必ずしも対話そのものの過程から即時にというわけではなく、対話と対話のあいだの時間にこそ意味がある。つまり、遅延が一種のインキュベーターとして作用しているのである。
「遅延」という時間的要素に加えて、飯島は「場所性」を強調する。飯島は「ノートという媒体の中で形成された現実世界とはかけ離れた二人だけの隔離的な場所」であると述べている2。ここにおいて二者は対等であり「間主観性」が維持される。飯島が目論むのは、こうした間主観性を絵画に展開することである。

転写の他者性
この展開においては「油彩で描くもの=相手・転写=自分という区別化を図りながら絵画内での溶け込みで関係性の曖昧さを表現」2することが企図されている。追加のインタビューでの飯島の解説は興味深い。ここで「転写」とされるのは、飯島自身の写真からの転写であり、転写を交えるのは、絵が自画像にならないためであるという。どういうことだろうか。飯島によれば、自分は相手の顔を知らないので、普通に油彩を描くと自画像に近づいてしまう。そうなることを予防する目的で、自分自身の写真の転写を用いるというのだ。自画像から遠ざかるために自身の写真を用いるという逆説的な手法。しかし、これはこれで非常に納得のゆく手法でもある。
写真は自身の顔の正確な転写であると言う意味において、多分に「他者性」を帯びている。自身の写真を見る時、「自分はこんな顔ではない」という違和感や嫌悪感を感じたことのある人は少なくないだろう。鏡像が左右反転した図像である以上、人間は誰一人として、自身の顔を直接に見ることはできない。その意味で「他者としての写真の転写」を「関係性の絵画」に溶かし込もうとする飯島の試みは正鵠を射ている。
固有性のコンテクスト
岡﨑乾二郎は著書『抽象の力』3において、岸田劉生の絵画が、「無形のもの」すなわち視覚対象として定位できないものの現出を目指すことで、キュビズム以降の問題群に沿っていた、と指摘している。岸田の絵が時に不気味に見えるのは、見慣れたものの姿が実は固定できない偶然的なものでしかない必然が現前するからなのだ。そこにあるのは、その対象との日頃のルーティン化された交渉=関係をはるかに超える潜在的な可能性である。
そのように考えるなら、飯島の手法は、あたかも岸田の制作とは逆立してみえる。岡﨑の指摘が意表を突くのは、岸田の絵画が一見したところ写実を意図しているようにみえるからだろう。いっぽう、そもそも手法そのものが写実たり得ない飯島の手法から、いかにして顔が生成してくるのか。ここで交換日記という手法が活きてくる。どういうことだろうか。
飯島によれば、交換日記から顔を生成する過程は以下の通りだ。相手の顔も声も知らない状態で、日記の言葉遣いなどからキャラクターを思い浮かべ、近しい人に当てはめながら、その人の記憶と絵を擦り合わせていく作業であるという4 。集合写真の絵の場合は特に、記憶の人を参照しつつ当てはめていくという。
なるほど、基本にあるのはキャラクターのようだ。ドローイングの作品は特に、漫画のキャラクターを思わせもする。ここで描かれようとしているのは、本人そのものというよりは、交換日記の中に出現する「交換日記人格」とも称すべきキャラクターなのだろう。ここにおいて、まさに交換日記である必然性が、最大限に活かされている。
SNSのように即時的で、相互性に開かれてみえるメディアは、まさにキャラ生成装置として機能する。SNSは実際には、それほど双方向性には開かれておらず、「いいね」によって可視化・数量化される集合的承認を獲得するためのメディアだ。そこでは、わかりやすく輪郭のはっきりした「キャラ」を立て、そのキャラに期待される発言を発信し続ける限りにおいて、承認の総量は増えていく。それゆえいったん立てたキャラから降りることは難しく、時には本人の意に反してでもキャラの同一性が維持されなければならない。
そうであるなら、SNS上の「キャラ」は、常に記述可能性に開かれていなければならず、その限りにおいて「固有性」は持ち得ない。そこにあるのは、岡﨑の言う「日頃のルーティン化された交渉=関係」が結晶化したキャラという存在でしかないからだ。だから私たちは、キャラとは真の関係を結び得ず、そこに「間主観性」は生じようがない。
これに対して「交換日記」は、さまざまな点でSNSと対立する。それはモノローグの交換のようでありつつ、実は真の意味での相互性に開かれている。私が「相互性」という言葉に込めているのは、結果的に双方に何らかの変化が起きるような動的関係性という意味である。この相互性を保証するのが、先述した「場所性(=ノート)」である。アナログメディアの強味は、このように交換不可能な場所を与え、反復不可能な遅延のもとで、複製も転送もできない言葉を交換できることだろう。そのような場所が、デジタルメディアとはかけ離れた不自由さのもとで、1回限りの「間主観性」のもと、固有性のコンテクストを発生する。飯島の試みは、その「固有性のコンテクスト」を顔貌のイメージへと結晶化させる試みではないだろうか。


「顔」という無限
私は最初の著作『文脈病』5において、「顔」について詳細に論じた。レヴィナスの『固有名』とドゥルーズ=ガタリの『ミル・プラトー』に依拠しつつ、顔は固有性を示すシニフィアンであると同時に、固有性のコンテクストそのものでもあり、すべての記号作用の根源に位置するものであることを詳しく論証した。その詳細については拙著を参照されたい。ただし、私による「顔」論は、あくまでも所与の顔を前提とした議論であって、そこには「顔の生成」という視点は乏しかった。漫画家の描く顔は固有のものでありうるかという問いについては、それがあくまでも「漫画家の顔」という固有性から分岐したものという立場から否定した経緯がある。
こうした視点から見ると、飯島の手法はむしろ正統的なものと言いうるかもしれない。それというのも、私たちが「顔」と出会う時、真の意味で「顔」を見ることは、きわめて困難でもあるからだ。もちろん顔の固有性は瞬時に伝達される。しかし、それでは済まないのだ。私たちは固有性を受けとった後、事後的に顔をパターンとして認識し記憶する。それは顔の一般的な「用途」が、人物の同定であるためだ。顔を同定のパターンとして、記述可能な要素に分解する際、顔の固有性は抑圧されることになる。岸田劉生の肖像画が不気味な印象を与えるのは、そうした記述可能性に回収されない潜在的要素にまで描写が届いているためだ。そして言うまでもなく「固有性」もまた、そうした潜在的要素の側にある。
それゆえ飯島は、あえて対象の「顔」を見ない。交換日記という特異な「場所」において、言葉だけを触手として、互いに探り、なぞりあう。パターンやイメージとしての「顔」にとらわれないがゆえに、この相互作用そのものから「固有性のコンテクスト」が生成される。それが「肖像画」に変換される時、それは飯島自身と対象の固有性のアマルガムとなる。まただからこそ、彼女の作品の多くは必然的にコラージュの要素を多分に含み、しばしば「表情」の見えないものとなるのだろう。こうした作品生成の営みが終わるのは、飯島自身が「固有性の手触り」を看取し得た瞬間ではなくて何だろうか。そのとき「顔」は、「我」でも「汝」でも「僕ら」でもない他者性、「面白ぇ生き物」としての他者性を帯び始めるだろう。私の考えでは、それこそが「真の肖像画」が兼ね備えるべき要素の一つにほかならない。
飯島はかつて、某教員から「絵画に期待しすぎている」と言われたとのことだが、愚かな発言をしたものだ。絵画とは顔を描くためのメディアであり、人間の顔は無限の可能性をはらんでいる。「絵画に期待する」とは「顔に期待する」ということであり、そうした期待なくしてあらゆる表現は不毛である。おそらく飯島小雪の試みは、いまだ途上にあるとみるべきだろう。間主観性の中から固有性のコンテクストを補足する試みは、今後も継続されていくはずである。そうであるなら私は、未来において飯島が生み出すであろう、無限の「顔」に期待したい。

- 自分と相手の関係性を描く 飯島小雪個展「僕らじゃない」イベントレポート
- 飯島小雪:研究内容テキスト
- 岡﨑乾二郎:抽象の力.亜紀書房,2018
- 2024年4月16日に行われた飯島小雪へのオンラインインタビュー
- 斎藤環:文脈病 ラカン/ベイトソン/マトゥラーナ.青土社.1998
Profile プロフィール

斎藤環
著書に 「文脈病」(青土社)、「社会的ひきこもり」(PHP研究所)、「ひきこもり文化論」 (紀伊國屋書店)、「生き延びるためのラカン」(ちくま文庫)、「ひきこもりはなぜ『治る』のか?」(中央法規出版)、「世界が土曜の夜の夢なら」(角川書店)、「ひきこもりのライフプラン」(畠中雅子との共著)岩波書店、「オープンダイアローグとは何か」(医学書院) など。訳書にヤーコ・セイックラ他著「開かれた対話と未来」(医学書院)がある。
Profile 作家プロフィール

飯島小雪 Iijima Koyuki
<主な展覧会>
2024年1月 秋田公立美術大学大学院複合芸術研究科修士課程1年研究経過展(秋田公立美術大学サテライトセンター/秋田)
2023年11月 「ー覗くー」(秋田公立美術大学サテライトセンター/秋田)
2023年2月 「尾道市立大学卒業作品展」(尾道市立美術館/ 広島)
2022年9月 「ACT アート大賞展 優秀賞グループ展 後半」(The Art complex Center of Tokyo/ 東京)
2022年8月 「gu- Small Art Festival」(松翠園大広間/ 広島/ ディレクション、キュレーション、作家)
https://lit.link/lightsnow30
Information
飯島小雪個展「僕らじゃない」
▼飯島小雪 個展「僕らじゃない」DM(PDF)
■会期:2024年3月8日(金)〜2024年3月31日(日)
■会場:秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINT
(秋田市八橋南1-1-3 CNA秋田ケーブルテレビ社屋内)
■主催:秋田公立美術大学
■協力:CNA秋田ケーブルテレビ
■企画・制作:NPO法人アーツセンターあきた
■お問い合わせ:NPO法人アーツセンターあきた
TEL.018-888-8137 E-mail bp@artscenter-akita.jp
※2023年度秋田公立美術大学「ビヨンセレクション」採択企画