アーツセンターあきたは、2024年12月から秋田市ふるさと納税返礼品の提供事業者として、秋田公立美術大学卒業生2名の作品をNFTアートとして提供する「秋田公立美術大学NFTコレクション」を運営しています。 この事業をはじめることになった経緯や狙いを、理事長であり秋田公立美術大学の教員でもある藤浩志とともに振り返りつつ、今後の展望について聞きました。
秋田公立美術大学NFTコレクションの経緯
三富:
秋田市ふるさと納税における秋田公立美術大学NFTコレクションは、秋田市、KDDI、秋田公立美術大学とアーツセンターあきたの4者が関わっているものです。秋田市はふるさと納税の枠組みを提供し、KDDIは作品のNFT化の技術提供を、アーツセンターあきたと秋田公立美術大学は学生・卒業生の作品を選定して提供するプロデュース役という関係性です。
少し経緯を振り返ってみると、そもそも2023年の夏に、美大事務局からふるさと納税で学生のNFTアート作品を販売できないだろうかという相談をアーツセンターあきたにいただきました。その時、相談を受けた担当者も私も、「これはないな」と思って受け流そうとしていたんです。
藤:
まず「何だろう?」という感覚でしょうね。
三富:
のらりくらりとしているうちに話が立ち消えるだろうと思っていたら、そうでもなくって。 それならニーズが学内にあるかを検証してから進めようと思い、学生と教員にアンケートをとってみました。私の中では、興味がないという回答が多勢で、それをエビデンスとして示せば話がなくなるだろうとも思っていたのですが、意外にも半数の学生が興味を示した。そこで、やらざるを得なくなり、真面目に勉強をしようと専門家を呼んでオンラインで勉強会を開催したのが2024年2月でした。
藤:
ちょうど1年前だ。
三富:
その後作家を選定しつつ、契約の要件をまとめて手続きをしたりして、2024年12月にリリースに至りました。学生に対するアンケートの結果を少しお見せします。 「NFTアートに興味があるか」、「ふるさと納税という枠組みで自分の作品をNFTアートとして提供することに興味があるか」を聞き、50人弱の回答を得ました。NFTアートに「関心がある」と回答したのは50%。ふるさと納税の枠組みにも、32.4%が「関心がある」と回答しています。ポジティブなコメントとしては、自分の作品を多くの人に見てもらいたいという意見や、卒業後の作家としてのキャリアを拓く可能性を開拓したいというものがありました。教員のアンケートは回答数が少ないので示しませんが、多くがネガティブなものでした。そんな中、藤さんは当初から学内で唯一この話に前向きだったという印象があります。なぜ、藤さんは興味をもったのかを伺いたいです。
藤:
なぜかというのは簡単で、知らなかったし、まだよくわかっていないから。1度ブームが来たのは事実だけれど、まだ始まっていないという感覚もある。新しいNFTが、これから10年後、20年後には、もしかしたら当たり前になっているかもしれない。それがわからないから興味をもつよね。わからないものに対して興味をもつし、やってみないとわからないというのが一番大きい。これまで恐らく99%の物事は失敗してきている。興味があって色々手は出すけれど、上手くいかずにチューニングを繰り返すというやり方をしてきて、そう考えると、最初からNFTがダメだと決めてかからないという感じじゃないでしょうか。
もう一つは、物の流通と情報の流通の仕方は明らかに変化していっている。配信サービスで映画を見たり、メールでデータを送ったり、クラウドサービスで原稿を提出したり、それが新聞紙面に掲載されたりと、実態のある空間や存在、イメージの所在が実態と仮想とを行き来してつくられている感覚があって。その上で新しい権利のあり方、所有のあり方にも興味がある。これは、僕自身の作品の延長にもある課題。例えば、1週間とか1ヵ月とかかけて空間をつくって、その後たかが1ヵ月とか3ヵ月くらいで撤収するでしょう。おもちゃのザウルスは廃棄物でつくられたものだし、物としても保存されないかもしれない。 残ってるものは写真だったりとか情報だったりとか物語だったりすると、そういうものが将来的にどう残っていくのか、残していくのか、それを誰が所有するのか、ここですよ。僕は美術館にも勤めていたし、美術館のコレクションの審議委員もやってるから美術館は何をコレクションするのかってなったときに、やっぱりNFTに可能性を感じざるを得ないわけ。もしかしたら新しい可能性がないかもしれないですよ。わからない。だってあんまり知らないし、NFTの作品なんて買ったこともないし、ビットコインすら持ってないし。やってないからまだわかんないんですよ。だからこそ興味を持ってる感じじゃないですか。

三富:
NFTアートの1次ブームがすごくあったわけじゃないですか。それは注目されていたんですか。
藤:
ちょっと引き気味加減で見ていて、すごくお金が高くついてて、すごく流通していってマーケットに入っていったじゃないですか。それで冷めたって感じはあったよね。
三富:
そのときは、先ほどおっしゃったようなNFTのアーカイブとか所有みたいなところの可能性までは意識していなかった。
藤:
NFTと直接繋がるかどうかわからないけれど、例えばメタバース空間とかデジタルとかゲームの中で、新しいコンテンツとして例えば車のデザインがデジタル情報として高値で取引されたりする。ちょっと違うかもしれないけど、ある希少価値のあるカードみたいなものが、コレクターにとってはすごく価値のあるものとして収集されていく。何かそういうものの面白さっていうのはあるなっていう気がしていて。一方で流通してどんどん値段が上がっていくのはあんまり面白くないかもしれないけれども、その反面デジタルデータの中とか、それを所有していることの意味っていうのが何かあるなっていうのは思ってきました。僕のザウルスなんかも、オンラインゲームに使ってる人たちがいて、名前とかついてるらしいんですよ。そういうのをいじってる人たちを見て面白いなと思って。そうやって新しいフォーマットにのせることで生まれる新しい遊びとか、新しい活動に面白さを感じている。NFTも、まだぼんやりしてるんだけど、そうなっていくと面白いなっていう気はしてたのはありますね。
三富:
秋田公立美術大学NFTコレクションの話があって、その感覚が再燃したということですか。
藤:
再燃したというよりも、そんなに信用してないし、動かないと思ってたから、そんなにしっかり関わるというよりは、どうなるかなって感じ。ある程度見ていくと、どこに乗せていくかとか、誰とやるかといった、プラットフォームの問題もでてくる。それはある程度時代が進まないと見えてこないし、どこに残すかという問題にもつながってくるよね。実態のある作品についても、作品の扱いが酷いコレクターに買われるよりも、いいコレクターに買われると作品も幸せだなってって感覚があるので、デジタルデータとはいえ、どのプラットフォームに乗せるかはもうちょっと見てみないとわからない。昨年2月のオンライン勉強会でも、この先5年、10年でインフラとして定着する可能性があるというような発言があったけど、もう一つきっかけがあれば、出てくるかもしれないとも思うよね。例えば、給料の支払いとかがビットコインでなされるとか、そういうのができるようになってくるとすれば、状況がガラって変わるじゃない。そっちの方が楽だったり、ポイントついたりとか、いろいろなメリットがあると人はそっちに流れる。本当にNFTとかメタバースっていうのがインフラとして定着し、アートの所有っていうのもデジタル空間で行われるようになる可能性も否定はできない。
可能性を捨てない
藤:
データの保存の問題もある。映像や写真は、フィルムからどんどんメディアが変化していって、今はクラウドがあって便利だけれど、サービスが終わるとなくなってしまう。だから2020年代の若い作家の表現とか、YouTuberとかもそうだけど、一瞬にして消えてしまう可能性がある。クラウドサービスが終わったら、どう誰が保証していくかもわからないっていうときに、もしかしたらNFT的なものがあって、履歴がついて、いろんな人が分配して所有してるってやり方っていうのは、実はすごい可能性があるなって思ってたりしたんだよね。 NFTが流行って、流通し始めた頃に、そうやってデジタルデータの元データやエディションをコントロールできたり、2次的流通したものが作家にもバックされる、そういう仕組みは何か可能性があるという気はしてたんですよね。保存の方法、デジタルデータの扱い、この悩みに対しても、もしかしたら可能性があるかもしれないって。わからないけれど、何もしないよりは試してみる。藁をもすがる気持ちで、僕らはいつも活動をつくってるわけだから、ちょっとでも可能性があるんだったら無視できないですよね。
三富:
今回協力いただいたのは卒業生の菅原果歩さんと真坂歩さん。菅原さんは、今回出品した写真のデジタルデータよりも、手書きで残してるフィールドノートっていうのをどうやってアーカイブしていこうかという課題感から協力していただきました。真坂さんは、真坂人形って土人形を作っている中で、それをデジタルという表現に展開したときに、どうまた真坂人形というものが変遷していきうるのかって言ったところの興味から乗ってくださって。そういう面白がってくれる卒業生であり作家と、まずスタートを切れたのはすごく良かったと思っています。
藤:
今回、卒業生の若い作家にお願いして、真坂くんの人形と菅原さんの写真を出品してもらった。これは面白いなと思ったんだよ。現役の学生に投げれなかったのは、リスクもあるから。教員に対するアンケートでは「学生の搾取にならないか」みたいな意見もあったみたいに、ここはちょっと強い人じゃないと相当難しいかなっていう気がしたんですよ。
真坂くんに関しては、人形は売れてるけれど、一個幾らの世界じゃない。100個つくっても幾らか。2次流通でお金がはいってくるものでもない。それを、デジタルデータにすることで、全然違う新しい流通が生み出されるかもしれないよね。真坂人形の場合、面白いのは、人形としてもあるけど、そもそもイメージが面白いんだよね。イメージの面白さがあると、実態のある人形もありながら、それを3Dのデジタルデータとして携帯の中に収まるみたいなのもあり得るわけじゃない。それはやっぱり試してみた方が、いいよねっていう気はする。 だから、僕は可能性のところでしか、ある意味動かないかもしれないんだよね。それは多くの場合失敗する可能性があって、それはもはや当たり前なんですよ。
三富:
ここまで藤さんの話を聞いてきて、すごく聞いてみたいのは、可能性を排除しないという藤さんの姿勢は素晴らしいなと思いながらも、何かに対峙した時に「可能性は高いのか、低いのか」みたいな、可能性の大小を測ることは多分あるんじゃないかなと思うんですけど。
藤:
ないですよね。そこの点については、可能性の大小じゃないけど多分僕の活動をずっと見てくるとわかると思うんですけど、みんなが排除したものを拾い上げる。
三富:
なるほど。可能性も廃棄物の一種。
藤:
みんながこれ駄目だろうって思うものに注目してしまう傾向が強い。廃墟もそうだけど。綺麗な家はあんまり興味ないし、みんなが可能性を感じているものは別にその人たちが感じてるからいいじゃない。でも誰も可能性を感じないものがあるとすれば、それはやらなきゃいけないんじゃないかなと思っちゃう。そこは新しい道じゃない。そういう視点では思ってるかもしれないね。だからNFTが流行りだすと、別にもう興味がなくなるかもしれない。今の状態では可能性がなくても、どこかが変化したら可能性が出てくるとか、誰も使わなくなった仕組みがあれば、その構造を変えてみるとか、組み合わせを変えてみるとか。みんなが見捨てたものから、すごい面白いものが出てきたとしたら、そこに燃えるわけだよね。なんかそういうささやかな喜びじゃないですか。天邪鬼ですね。
三富:
藤さんが見捨てなかったお蔭で、なんとか昨年12月にリリースして、今は少し真坂さんの作品が売れている状態です。
藤:
これってどのくらいやるのかな。
三富:
関係者からは売り切りたいという声をいただいています。
藤:
腐らないし、倉庫もいらないしね。
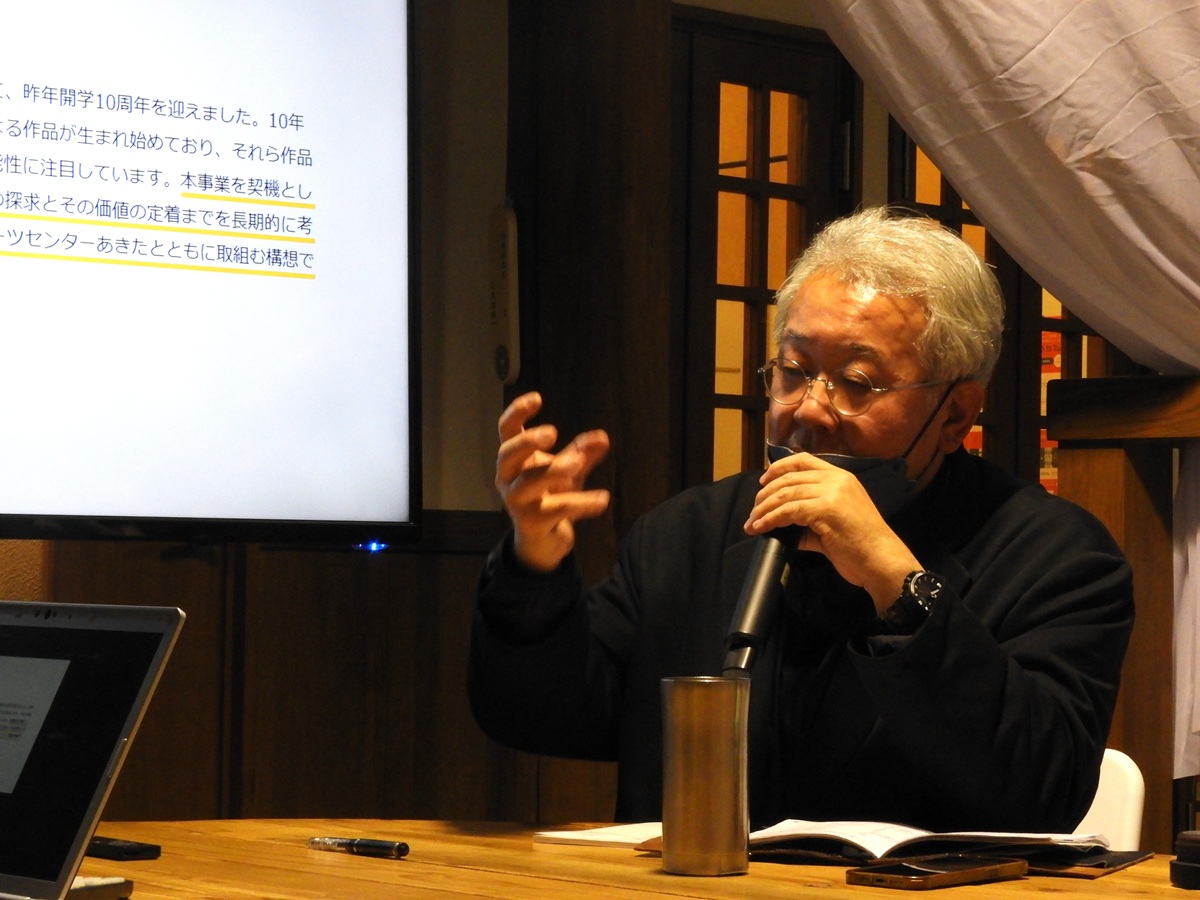
今後の秋田公立美術大学NFTコレクション
三富:
2つ目の質問は、今後どうするか。藤さんのイメージを聞かせてください。
藤:
2人とも卒業生で、これから作家として動き出そうとしてる人たちで、どうにか生きていく方法も探さなきゃいけないという、ある意味切実な問題もありながら、本当につくるっていうことに対してすごく正直にというか、誠実に向き合っている。彼らが新しい方法として乗ってきてくれて、今回2つのケースができたわけじゃない。そうすると、今度は全然違うケースをやりたいよね。
三富:
全然別のケースっていうのは、例えば?
藤:
どんなイメージかはわからないけれども、例えば、景観デザイン専攻の場合、図面やプランをどう保存するかっていうのもあるし、学生のプランや提案みたいなものをNFTとして残していくのは面白いかもしれない。デジタルの中でどうなるかわからないけれど、ゲームを制作している学生も増えてきていて、そういうものをどうNFTにできるか、どう流通するかというのは見てみたい気がするかな。
三富:
最初このお話を聞いたときから、NFTアートというような新しいテクノロジーに反応し、かつアートっていうところに興味を持つ層と、ふるさと納税っていう仕組みの購買層は、あんまりマッチングしないんじゃないかなっていうのは思っていました。
藤:
そうだね。どういうものを、しかも秋美発で、どういう可能性があるんだろうなっていうのは考えるよね。漫画とか映像とか、デジタルで作品をつくっている学生は多いから、何をどういうふうに配布できるんだろうっていう感じだよね。ちょっと欲張りですけど、できれば秋美らしい作品みたいなものをちょっと探していきたいなとは思うんです。秋美らしい作品っていうのがもしあるとすれば、願わくばですけれども、もう今まで見たこともないようななんじゃこれはというような表現であるとか、物のあり方とかデジタル情報のあり方とか、作品のあり方そのものの面白さだよね。僕らはさ、今後どうするってそこの中身のコンテンツまで考える必要はなくて、それは面白い卒業生とか、学生とかの作品を、どうやってNFT化していくのかっていう実験を繰り返していくのが重要な気がするね。どうせ儲からないわけだから、いろんな取り組みをやってみると何か外から見るとこんなことやってるっていうその意味不明さみたいなのが秋美の面白さに繋がったり、秋田市の面白さに繋がっていくっていうのはあるかもしれないけどね。
作品や活動のアーカイブは、大学のアイデンティティになる
三富:
この案件に乗ろうと腹を括ったのは、アーカイブについて考える契機になるからという意見もありました。そこを作品のリリースにあわせてちゃんと伝えた方が良いだろうと、プレスリリースにも「この事業を契機に、アーカイブについて考える長期的プロジェクトに取組む構想である」という一文を盛り込んだんです。この点について、藤さんのご意見を伺ってインタビューを締めたいと思います。
藤:
大きな話になっちゃうけれど、例えば美大や作家のあり方や存在は、秋田市や秋田県のそれと同じだという風に思っていて。ブランディングというかもしれないし、存在意義に関わる問題と言えると思っている。遡るとミュージアムの発生は、実は日本という国ができたときと関わってくるし、その国や地域が何をつくり、何を生み出してきたのか、どういう人がいたのか、地域の特性や独自性をアイデンティファイする(見分ける・識別する)ことにつながっている。そのために何を、どう保存するか、記録するかということが重要になってくるんですよ。
秋田公立美術大学も開学から10年が経過して、卒業生がでてきて、作家として活動を始めるようになってきて、これから大学がどうあるのかってなった時に、これまで何をやってきたのか、そこで何がなされてきたのかということをちゃんと見て、活動を保存し、記録していかなくてはならないっていう話なんですよね。
三富:
ありがとうございます。 秋田市ふるさと納税における秋田公立美術大学NFTコレクションの事業は、今後も継続予定ですので、是非ご注目いただければ幸いです。
Information
秋田公立美大卒業生NFTアート作品の秋田市ふるさと納税返礼品提供事業
秋田公立美術大学卒業生によるNFTアートを、秋田市ふるさと納税返礼品として提供します。
■返礼品提供事業者: NPO法人アーツセンターあきた
■出品作家:真坂歩、菅原果歩
■協力:KDDI株式会社、KDDIアジャイル開発センター株式会社
■出品サイト:
ふるさとチョイス
楽天ふるさと納税
さとふる
JRE MALLふるさと納税
ANAのふるさと納税
※本事業においては、Web3サービスプラットフォーム「αU」を利用いたします。




