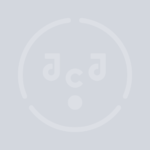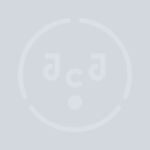磯崎未菜「singing forever 高砂」
磯崎未菜が今回のプロジェクトの発端とした高砂は、仙台市内を流れる七北田川が仙台湾に流れ出る河口付近の地名である。能の高砂の舞台となる兵庫県の高砂市と河口の景色が似ているとして名付けられたようだ。縁起の良い高砂という地名は、他にも全国にいくつかある。しかし、仙台の高砂地区は、東日本大震災で津波の被害を受け、河口付近は広範が災害危険区域とされたため、今後は過去のような住宅地に戻ることはないだろう。仙台の高砂は、謡曲にあるような悠久のイメージとはかけ離れている。
磯崎がこの場所に注目し、2018年に仙台に移り住んだ時点で、すでに震災から7年が経過している。震災以後の高砂の変化を克明に追いかけるには少々時間が経ちすぎていることは否めない。ただ、彼女の関心は震災の記録とは別のところにある。これまで磯崎は「場所」の歴史や由来の調査に基づく「うた」をつくり、プロモーションビデオのような映像とともにあらわしてきた。東京の団地を舞台にした作品に続けて、震災後の福島でも制作し、次なる場所を求めて北上するように仙台を訪れている。過疎化の進むニュータウンにせよ、原発事故後の福島にせよ明らかなのは、磯崎の関心は、近代化にともなう土地との関係性の失陥にあることだろう。彼女はdestinyではなくfateとして近代を捉えていると思われるのだ。

そんな磯崎の活動を、わたしは「勝手に民謡プロジェクト」と理解している。つくったうたを、地域に根付かせるように、住民と一緒に歌うといった演劇的なパフォーマンスはせず、うたは中空にとどめおかれる。そして、うたを届ける他者を特定し、交流などをすることで、具体的な他者の名において情感が発生することを抑制している。また同時に、そもそも届けるべき他者など容易に見出すことはできないとする自閉的な精神もかすかに見え隠れする。磯崎の過去の作品において、うたは概ね作者自身に向けられている。あるいは、ごく親密な一名程度の誰かとだけ共有しているように思われる。そうして、あたかも人類が滅び去った未来の廃墟における一人遊び、あるいはままごとのようにして歌う姿を、観客にプレゼンテーションするのである。磯崎は、場所の過去に触れることで、うたの着想を得ながら、より未来からの照射のように提示することで、物語の着地を曖昧にし、不思議な浮遊感を生み出している。さて、こうした表現をおこなってきた磯崎が、単体の作品展示ではない今回のプロジェクトではどのような展開をさせたのだろうか。

展示会場は秋田市内の製菓店「高砂堂」と、秋田公立美術大学のギャラリーBIYONG POINTの二箇所である。今回の展示は、能の「高砂」の物語進行にあわせてつくられている。高砂堂には、あらすじを紹介する紙芝居の映像≪高砂、出発のとき≫と、兵庫の高砂と宮城の高砂を一枚の地図絵に合成した≪ふたつの高砂≫が展示されている。この2つの作品は、今回の展示のプロローグとして重要なのだが、ギャラリーのほうには展示されていないため、高砂堂から鑑賞をはじめなければ、物語の「起」にあたる部分には触れることができない。これは致命的なミスかと思わないでもない。しかし、起承転結のような物語的構造をもつ展示構成でありながら、リニアな鑑賞体験をもたらさないことは、あらかじめ作者が想定したことのようにも思われるのである。
それは、ギャラリーの最初の展示作品である≪淡路、追う/逃げる/だます/ふりをする≫からもわかる。この作品は、淡路島をモチーフに独自に開発したテーブルロールプレイングゲームの記録映像である。4人の男女によっておこなわれているこのゲームは、まずそのルールを理解するだけでも長時間を要する。さらに映像は、見る者をプレイヤー同士の豊かな会話に没入させ、やがてゲームの終わりというカタルシスをもたらす。そして、映像の脇に置かれた冊子状のゲームシナリオは、神話の時代から現在にいたるまでの淡路島を取り上げており、読み物としても妙に充実している。確かに謡曲では、播州高砂から出帆ののち淡路の島影をみながら船は進むとあるが、要は通り過ぎたというだけである。筋に沿うのであれば、淡路島をあつかったこの作品はサブストーリーである。にも関わらず、ここでは調査に基づいて徹底的に淡路島を掘り下げており、明らかに今回展示された作品中で最も熱量をもってあらわされている。


また、続く映像作品、≪鳴尾、見たものはすべてうたになる≫も同様の脱線をみせる。謡曲では「遠く鳴尾の沖過ぎて」とあり、例によって、船は通過しただけだ。しかし作品では、鳴尾にちかい甲子園球場がフォーカスされ、2名の人物が、阪神巨人戦で熱狂する甲子園の三塁側と一塁側のアルプス席にそれぞれ陣取る。そして、ベンチ側の球団が攻撃している間中、そこから見た景色を短歌に詠むのである。演者たちは、挙手してから詠み始めるのだが、その挙動は、応援する観客達にまぎれて不思議と違和感がない。野球の試合を短歌として描写しながら、決して状況そのものには没入しない存在としてふるまうのである。熱狂的な状況に身体をおきながら精神の距離をとろうとする姿勢は、現在のポピュリズム的なメディア環境を揶揄するようにも受け取れるものであり、ここでも謡曲を離れた新たなコンセプトが提示されている。
これら個別的に充実しながら展示全体を破綻させるような映像作品によって、もはや仙台の高砂との連続性も、能の高砂の物語性も輪郭がにじみ、展示はリニアリティを失う。それこそゲーム体験になぞらえれば、いくつも枝分かれするサブストーリーの達成に夢中になり、もはやメインストーリーを進められなくなる感覚だろうか。磯崎は、震災という強固な物語性と、津波の被災地という具体的な場所に端を発しながら、淡路島の作品がタイトルで示すように「逃げる」、「だます」、「ふりをする」ような展開を選択している。これは不可解なようではあるが、わたしはこの点にこそ、磯崎の優れたバランス感覚を見て取る。


近年の主流でもあるコミュニティ・アートは、他者としてのアーティストが特定の地域や集団に入り込み、住民らとの共存的な関係を作り出すことで、停滞していたコミュニティにバイタルをもたらす。という表現の形式や手法として定着しつつある。具体的な人同士の関係性に触れるがゆえに、結果として、社会的な意味での「連帯」や「共感」など「善」なるものに収束せざるを得ない。そうでなければ、アーティストは既存のコミュニティの破壊者にすぎないのである。しかし、善なるものの引力は、往々にして表現者の意思よりも強く働くのである。さらにはそのことを認識している行政に政策として利用されることもある。毒であり薬でもあるファルマコンになぞらえられる芸術表現が、あらかじめ有用性に取り込まれ、回答のベクトルを限定されるのは酷なことだ。ましてや被災した地域を舞台とすれば、その困難は言わずもがなであろう。磯崎は、こういったコミュニティ・アートの今日的な課題を認識し、まわり道を意図的に選択している。そうすることで、パターン化した方法論に陥ることを避け、メタ的な自らの立ち位置をわずかにずらしていくことで、同時代性への言及を試みている。
美術史という近代化の歴史が終わったあとの現代のアートについて、なお、過去の表現を参照してしまうメタ的な視点こそ、磯崎にとってのリアルな身体感覚なのだろう。他方で、知識や記号としてのアートを意識的に捨象して、地域性のなかに確かなものがたり行為を見出していく姿勢もある。これは震災以降の表現の特徴のひとつと言えるものである。だが「地域性」なるものもまた、すでに記号化されてしまっているのだ。震災以前の仙台の高砂も陸から眺めれば典型的なロードサイドであり、現代の地方都市を構成する記号的な場所ではなかったのか。そうならば、アートの記号性と、地域という記号性をジャグリングのように操作することで、そのいずれにも符合しない領域を見出すことができるのかもしれない。あるいは、端緒から直線的にのびていく物語にこだわらず、むしろ枝分かれを自然なことと受けとめ、サブストーリーの枝先に果実を実らせてみる。こういった手法によって磯崎は、8年目という時性を無効化しつつ、ポストヒストリカルな認識にも向き合っているように思われるのである。

ともあれ、展示は、謡曲のとおり、住吉(すみのえ)に着く。最後に展示された映像≪住吉、面の内より謡う≫は、能「高砂」の最後の場面、舞い踊る住吉大明神の視点で、仙台の高砂を見たものだ。能の面越しに、荒涼とした河口付近の原野とその彼方にあるコンテナやガントリークレーンや煙突などが映される。展示の最後にやっと登場した仙台の高砂は、あたかも遠い過去の風景のようでもあり、高砂を傍観し続けるしかない磯崎の身体をあらわすかのように、行き場のない目線が右往左往している。ここまで本筋と無関係に充実していた淡路島や鳴尾にくらべ、この映像にはうたもなく寂寞としている。展示の最後に位置しながら、おそらくは、この作品こそが高砂プロジェクトの真のプロローグなのだろう。能の物語進行を借用しながら細部を肥大させ、また会場をふたつに分けることで展示の構成上もまわり道をつくりながら、磯崎は、最後にプロジェクトのはじまりを見せようとしている。うたになるまえの原初の風景として。
その意味で、このプロジェクトはまだ未完である。そして今回の展示によって大いなる前奏を終え、高砂のうたはこれからはじまっていくのだろう。
清水建人(せんだいメディアテーク主任学芸員)
Profile
Information
磯崎未菜「singing foever 高砂」
■会 期 2019年6月8日(土)〜8月18日(日)9:00〜18:00
■観覧料 無料
■会 場
秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINT(秋田市八橋南1-1-3 CNA秋田ケーブルテレビ社屋内)
高砂堂(秋田市保戸野通町2-24)※毎週日曜、毎月15日定休
■主 催 秋田公立美術大学、NPO法人アーツセンターあきた
■協 力 CNA秋田ケーブルテレビ、株式会社高砂堂
■デザイン 根本 匠