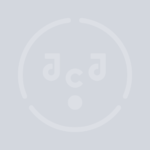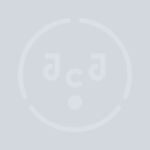イメージの再創造から「動く森」へ:
長坂有希による二つのプロジェクトの間に
1. 菅江真澄の図絵を再考する
人はなぜ、自分が生まれ育った場所ではないどこかへ、旅をするのだろうか。旅は、衣食住という生活要件を揺るがし、慣れない風習や景観に感覚をさらす。旅は日常の営みを撹乱し、歴史についての認識に亀裂を走らせる。様々な疲労や、混乱や、出費が生じることは自明であるにも関わらず、私たちは好奇心や仕事の必要に駆られて旅をする。もちろん、難民や移民がそうであるように、政治的・経済的な事情によってやむなく移動を続ける場合も少なくない。旅や移動は、人間性の深い部分に潜む未知の現実への憧れや、自由への希望と結びついている。
どのような社会も、そのルーツに移動の記憶を秘めている。私たち現生人類は、決して一つの場所に留まり続けてきたのではなく、常に何らかの理由で断続的な移動を続けてきた。直立二足歩行という長距離移動に適した身体を手に入れた人類は、共通の故郷であるアフリカからユーラシア大陸を経て、オセアニアや太平洋の島々へ、さらにベーリング海峡を超えて南北アメリカ大陸にまで拡散していった。移動や旅は、定住に先立つ人間性の要件と言っても良い。移動することがなければ、私たちの祖先は、数々の危機や変化を生き延びることはできなかっただろう。ユーラシア大陸の最果てに位置する日本列島においても、旧石器時代以来、三万年以上におよぶ移動の記憶が、各地に刻まれている。極東の日本列島では、多様な集団が絶えざる移動や交易・交換を続けることで、長い時間をかけて文化的混淆を続けていった。
住民が自由に旅をできる状況ではなかった江戸時代においてさえ、日本社会は東北や蝦夷地を旅した、菅江真澄のようなユニークな旅行家・観察者を生んでいる。菅江真澄は、故郷の三河(現在の愛知県)を出発して中部地方へ、そして北東北に北上し、そこからさらに蝦夷地(北海道)に向けて移動生活を続けつつ、最後は北東北の各地に滞在し、秋田で生涯を遂げた。彼は、自身の先駆者である日蓮聖人の弟子・日持上人や、各地に膨大な仏像を残した仏師・円空といった先人たちのことを、常に意識していたという。真澄によって残された旅人の知覚と思考の痕跡は、日記や地誌に散りばめられた図絵や文章、和歌として、現代に至るまで貴重な博物学的価値を伝えている。江戸後期という時代にあって、彼は当時の知識や物流の集約地であった京や江戸には長居することがなく、後半生の生涯をもっぱら「北」への旅と観察に費やし、そこからユニークな表現の空間を立ち上げたのである[1]。
それまでほとんど歴史的記録が残されてこなかった北方の文化を、彼は自身の眼で観察し、数多くの日記や地誌、随筆を編んだ。しかも彼は、まだカメラも録音機もスケッチブックもない時代に、筆と紙をつかって景観や風物を描き、後世に活き活きとしたイメージを残してくれた。彼が描いた色彩豊かな風景画・博物画には、江戸時代後期における地域社会の様子だけでなく、当時の人びとの信仰や伝承、動植物との深い関係性が、見事に描き出されている。
柳田國男や宮本常一を始め、真澄の伝えた地域の伝承知に学び、日本列島各地を旅した知識人は少なくない。明治時代以後、真澄の著作や表現を読み解き、その方法論を継承することによって、近代的な学問としての民俗学・地域史学・考古学といった学問領域が発展してきた。しかし、真澄の残した図絵に関しては、ごく少数の例外を除き、まだ民族誌的な記録以上の読み取りがなされていないのではないだろうか? 真澄が描いたイメージや表現を芸術的創造の視点から再考し、そこから新たな可能性を汲み取っていくとすれば、いったいどのようなアプローチが可能だろうか?
2.「写す行為」としてのドローイング:長坂有希による再創造
菅江真澄の描画には、川・海・湖・泉などの水が頻出し、土壌や岩石などの地質と共に、特徴的な樹木の形が記録されていることが多い。それらの多くは、ゴツゴツとした荒々しさや、画面を横断する奇怪な形状をとどめている。あらかじめ様式化された花鳥風月の美しさに慣れた都会人の眼には、これらの田舎の景観は無骨に、味気なくみえるかもしれない。しかし、果たして本当にそうだろうか?
アーティストの長坂有希が、2019年の秋から秋田に滞在して行ってきた菅江真澄に関する追調査や再制作の方法は、こうした紋切り型の感想を抱きがちな鑑賞者の感性を、粉々に破砕するような、シンプルな肯定感にあふれていた。長坂はまず、多くの人がそれを菅江真澄本人のものと錯覚しがちな写本の類から視点を移し、あくまでも彼の自筆図絵という媒体のみを通して、そこに描かれた現実をとらえ直そうとする。さらに、菅江真澄のテキストに描かれた、旅人としての彼の知覚や情動をなぞるかのように、実際に真澄の訪れた場所に赴き、それぞれの土地に潜在する記憶や生命活動の痕跡を辿りながら、描かれた特徴的な「木」のイメージを「写す」ことに挑戦する。

2019年から20年にかけて、秋田市内で行われた長坂有希の展示(「木:これから起こるはずのことに出会うために/Trees: Audition for a Drama still to Happen」2019年11月16日~2020年1月12日、秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINT)では、菅江真澄がかつて描いた七点の木の図絵を原画として、改めて抽象化された線によって描かれた木のドローイングが展示された。しかし、長坂の作品が単に原作を真似た複製イメージではなく、習作的な模写にもなっていないことは明らかであった。長坂は、真澄のものとは異なる描線を保ちつつ、彼が描いた「木」のラインを意識的に描き直すことで、オリジナルの図絵やその複製写本に対するラディカルな距離を表現する。その創作姿勢は、あえて図絵のイメージから切り離され、会場内で閲覧できるような状態でテキストのみを掲載した冊子の冒頭で示された簡潔な主張によって言い尽くされている。
約二百年前にこの土地を歩きまわり、多くの物事を書き残してくれた菅江真澄へ、そして、個として存在しながらも他者や他の生きものたちとつながる勇気を持つ私たちへ[2]。
長坂はこの冊子で、菅江真澄が書き残した記録を手掛かりとして、彼や彼の描いたものたちが生きた時代や空間を想像しつつ、膨大な時間の層の中に埋もれた出来事の膨大さに思いをめぐらせている。彼女はそこで、住民でも旅人でもなく、いつまでそこにいるかも定かでない一時的な居住者として佇みながら、日記や地誌、図絵を描く菅江真澄という個人に対峙しているかのようだ。また、会場に展示された木々のイメージは、明らかに菅江真澄の記録に寄り添っているものの、敢えて異なる筆致を施すことで、時間によって大きく隔たれた現実を異化しているようにも見えた。
さらに、真澄の眼差しの先にある「他者や他の生きものたち」の暮らしぶりを観察し、「写し」によって真澄の表現の純粋さを異化することによって、長坂はアカデミックな記録からもアーティスティックな表現からも零れ落ちてしまう、生命と非生命がせめぎあう現実の渦中に飛び込んでゆこうとする。
重要なことは、そのような現実の裂け目は、もともと真澄の表現自体に含まれていたものであるということだ。長坂はただそれを、自らの足で歩き、目で見直し、手で描き直すことで、シンプルに増幅しようとする。つまり、真澄の視点に個人として向き合い、理解を深めようとするなかで、場所性そのものと再会し、表現上の新たな様式化へと、自然に導かれているように見える。たとえば「星山清水のねずこの木」は、美郷町の本堂城回・星山家の敷地にある樹齢四百年の老木を描いた作品で、真澄が「月の出羽路・仙北郡二」に描いた時代を思いつつ、この木の来歴やその後の出来事を思わせるイメージである。真澄の図絵を見ると、この木の前に大きな池があったことがうかがえるが、現在はその規模はほんの小さな範囲に縮小している。かつて豊富な湧き水を湛えていたこの土地も、老木の根元から湧き出すわずかな清水以外は枯れてしまっていた。長坂は、この作品について、次のように書いている。
人々は昔、水を求めて井戸を掘り、その周りに木を植えて、木の根が水を吸い上げることで地下の水脈が変わり、井戸に水がもたらされることを願ったそうだ。また、すでにある湧き水を守るために、周りに木を植えたそうだ。清水が先だったのか、木が先だったのかについての答えを私は見つけることができなかったが、二つのものが相互関係を保ちながら共存していることは見て取れた。その関係性は、清水と木を守り、湧き水を使い続けてきた人々によっても支えられてきたはずである[3]。
井戸を掘り、ねずこの木を植えた現地の居住者は、地下の目に見えない世界を想像することで、たしかに水脈という次元に働きかけようとしたに違いない。そのとき、清水は鉱物や植物の間で、渾々と湧き出していた。そして、異なるもの同士が、相互関係を保ちながら共存することを、真澄自身もたしかに描いていた。二百年前にこの地を訪れた真澄の足跡を追うように、長坂は同じ場所を訪れ、清水と木の絡まり合う関係を観察する。二百年の時を経て大きく変化を遂げているが、そこには真澄が見たときと同じ木が屹立し、彼女を迎えてくれたことだろう。

観察と「写し」に基づくこのような長坂の方法論は、人類学者のティム・インゴルドが述べる「徒歩旅行」の説明を思い起こさせる。徒歩旅行は、あらかじめ海図上に配置された定点から別の点へと航海を続ける船の旅とも、ある地点から別の地点をつなぐ空中の最短経路を横切る空路の旅とも違っている。これらに対して徒歩旅行は、「以前に通ったことのある道を誰かと一緒に、あるいは誰かの足跡を追って辿り、進むにつれてその行程を組み立て直す」試みであると、インゴルドはいう[4]。
菅江真澄が生涯をかけて行った旅もまた、実はこのように絡み合った行程や時間の再編成の連続であった。彼が断続的に行った「徒歩旅行」は、実際に彼が見聞きした自然界の風物、そしてさまざまな先人の言い伝えや断片的な知識を総合し、絵画と文章によってみずからの行程や知覚を表現する行為と一体になっていた。菅江真澄はそのとき、今日のアーティストや人類学者・民俗学者のようにある地域に滞在し、リサーチを通して制作する主体を先駆けている。そして、菅江真澄の旅を辿り直し、彼の描いた樹木を描き写すとき、長坂もまた徒歩旅行者のように先駆者の足取りを見つめ、その方法論をなぞることで他者や他の生きものたちとの関係を再構築している。

3.植物の他者性をめぐって
菅江真澄の記録として現代に伝えられたいくつかのイメージの中には、彼が見たかもしれない、数百年同じ場所で生き続けている木もあれば、すでに失われた木もある。たとえば真澄が「勝地臨毫・雄勝郡六」に書いた伝承には、朽木に若い木の枝をさして通ると言う「山の神の手向け」または「山の神の花立て」という口碑が記されている。長坂はそれらをたどりながら、想像力をさらに拡張する。
朽ちた木が土壌になり、手向けられた枝が根付き、大きくなって、今でもどこかに立っているかもしれないと想いながら森を歩いた。山の神に枝を手向けていった人々の想いや手振りが、今私の目の前に広がっている森を形作ったのかもしれないと思うと、この朽ちた木と私のいる場所につながりができたような気がした[5]。
例えばある種の木々は、土地の歴史や景観そのものと深く結びつき、世代を超えた伝承に結び付けられている。だから、木にまつわる歴史や記憶を紐解くことは、その土地に暮らす人びとの暮らしの現実を超えて、今は記憶から消えてしまった先住者や祖先の歴史を、深い次元でとらえ返すことに繋がってゆく。故郷を離れ、見慣れない土地を訪れた個人が、その土地に根を張った巨木や老木にまつわる伝承に惹かれるのは、一人の人間の個体性が朽ち果てた後、世代を超えて語り継がれてきた現実に感応するからかもしれない。こうした直観は純粋に想像の次元に括り付けられているのではなく、常に潜在的な歴史の現実性と関連し、未来へと開かれている。
先人・菅江真澄の足跡を追いつつも、それを地図化するのではなく、木という生物を通して彼の残した図絵の特異性に迫ろうとする長坂のアプローチは、どこかイタリアの哲学者であるエマヌエーレ・コッチャの哲学を思わせるところがある。コッチャは人間中心に構築された哲学や思想を乗り越える中で、動物に先立って世界に発生した植物に着目した。コッチャは、植物が土壌と天空、あるいは地中と空中という、根本的に異なった二つの世界を結ぶ媒介者であり、「環境同士、空間同士を結びつける」生物であることを強調している[6]。コッチャによれば、植物は、光に浸され、他の動植物との可視的な関係を結ぶ「中空の生命」と、地下に隠退し、真っ暗な潜伏的領域であらゆる形態の生命と共生を営む「冥界的な生命」という二重の生命構造を持つという。例えば一本の木は、その根・幹・葉・花・果実を通して地上と地下という二つの異なった環境を相互交流・相互浸透させ、他の生物が生きることのできる空間そのものを作り出す。こうした媒介性は、菅江真澄の図絵だけでなく、長坂が真澄の足跡と筆跡をたどって再創作した木のイメージからも、たしかに感じられる要素である。

2019年の秋の展覧会で実現されたインスタレーションによる長坂の表現は、単なる視覚的な平面表現でもなければ、社会的なコミュニケーションの中に溶解する脱視覚的表現でもなかった。その展示は少なくとも過去の二百年の間に起こった人間の歴史と非人間の時間を媒介するだけでなく、個人の一生を超えて持続する時間の流れやその間の記憶の蓄積、そこから派生する事物の連鎖や複数種の織りなす生命活動の網目を感じさせる。さらに、長坂の作品は木という植物を描くことで定住と移動、過去と未来、生命と非生命を鏡面のように反転させ、これから起こるかもしれない未知の出来事や、生まれてくるかもしれない生命の予感を映し出している。黄色の光に包まれたこの空間は、まさにこれから上演されるドラマの先触れであったのだ。
コッチャによれば、世界というシステムは常に「呼吸」を続けていて、そのことによって生物は、異なる存在と相互に支えあうことができるし、相互に浸透しながら新たな世界を更新し続けることもできるという。実際地球上では、動物以前に登場した植物が大気を「呼吸」することによって、ほかの全ての生物が生息することのできる環境が整えられてきた。つまり、大気や大地の循環を恒常的に生み出してきたのは植物であり、木である。ここで言う世界とは、ほかの全ての生物が、これから起こる出来事と対峙することのできるような、最も根本的な物質性の基盤を意味している。こうした基盤を作ってきたのは、もちろん人間ではない。「すべての有機体は、世界を産出する一つの方法の発明にほかならない[7]」とコッチャは考える。その発想は、たとえばハイデッガーの哲学に見られるような、人間・動物・鉱物の三者とすでに対象化された世界の関係を中心に組み立てられてきた、西洋の形而上学に対する鮮やかな批評として、階層化される以前の「混合する宇宙」のイメージを提示している。
神と人間の下位範疇として、動物と非有機物の階層を設置するとき、西洋の形而上学はしばしば植物や菌類のことを忘れ、あたかもそれが、人間や動物のための隠れた脇役のような扱いに還元してしまう。しかし、地球の歴史をたどってみれば、これは明らかに不公正な階層化だということがわかる。なぜなら、コッチャが指摘するように、動物界に先立って世界制作に参入し、地球上の大気の環境を準備したのは、植物界の活動にほかならないのだから。しかも、大量の植物が微生物や動物とともに朽ち果て、気が遠くなるほどの長い時間をかけて地上に堆積していくことで、次世代の生きものが生息する大地が準備される。さらに、人間が大地から汲み上げ、エネルギー資源として利用する石油や石炭もまた、そうして朽ちていった生物の死骸の堆積物であり、かつて産出された世界の一部でもあるということを、忘れるわけにはいかない。
「植物の哲学」によってダイナミックに生成する世界を描写するコッチャのように、菅江真澄は水や土や木を描くことで、遥か昔に産出された世界の奇跡を、そしてその後の歴史を通じて更新されて来た世界の在り方を、驚きをもって描こうとしたのではないだろうか。真澄はその鋭い観察眼によって、江戸時代の秋田を透視して遥か古代へと続く地域の「いにしえぶり」を発見した。そして、その真澄の描く図絵を写し、彼の足跡をたどる長坂の視点もまた、現代と江戸時代後期を結び、さらにその先へ、そして人間の歴史を超えた局地的な生態系のドラマへと、私たちの視点を無限遡行させる。とりわけ木々は、個という単位を超えて空間同士を結びつけ、人生という尺度を超えて異種の生命の相互作用に出会わせてくれる。このように、異なる存在の領域を媒介し、光や気温や湿度といった条件によって場所をつくる木の存在は、人間の集住する空間にとっても、根本的な重要性を持っている。一本の、あるいは多数の木のなかに、私たちにとって重要な他者性を認める時、芸術表現は人間を中心とした世界観から解放され、未知の可能性を手に入れるかもしれない。
4.「森の移動」という視点へ
秋田での最初の展示が終了した2020年の初春、長坂はさらにそれまでの制作構想を拡張し、横手にある秋田県立近代美術館で開催される予定の展覧会「ARTS & ROUTES -あわいをたどる旅-」へと向けた、さらなるリサーチを始動していた。新型コロナウイルスの被害が世界に拡大し、日本の都市圏にも広がろうとしていたこの時期、長坂は植物学者への取材や、青森での埋没林調査を通して、ある重要な知見を探ろうとしていた。それは人間や動物ばかりではなく、植物もまた長期間を通じて地表を移動していくものであり、ある局地的な舞台を通して、生成と消滅を繰り返す存在である、という森林生態学的な知見である。

空間を自由に動くことのできる動物との比較により、植物は長い間ある土地に縛り付けられた不自由な存在だと見なされてきた。ところが、近年の森林生態学は、森林を構成する草木や樹木の個体群が、光・気温・湿度・水分などの条件の変化に伴ってダイナミックに移動し、世代を超えた群衆的活動を展開してきたことを明らかにしつつある。もちろん地表は寒冷化や温暖化を繰り返すだけでなく、火山の噴火や地震・津波の勃発など、大きな不可抗力によって変化する。そのなかで、かつて人為的な活動によって達成された条件が、何らかの理由で遺棄されたことによって変化し、新たな植生や景観をもたらすこともある。
長坂が掲げる「これから起こるはずのこと」とは、そうした人間以上の世界へと想像力をめぐらせる方法であり、過去と未来を結ぶ構想でもある。菅江真澄という過去の旅人の足跡を辿り直し、その旅路を未来の出来事へと反転させる作法は、たとえば埋没した最終氷期の森林を掘り起こし、未来の森の行方を占う行為にも似ているかもしれない。
その試みは、あらゆる科学と想像的な物語をつないで紡がれる、未知のエコロジー実践へと継承されて行くだろう。私たち鑑賞者は、真澄や長坂がそうしたように、個々のペースで独自の「徒歩旅行」を続けることで、場所に支配されるのでも、支配するのでもなく、場所そのものをつくる世界制作の活動へと、導かれていくかもしれない。そのとき私たちは、人間だけでなく、他者や他の生きものたちとの共通の家である環境そのものが移動するという現象の秘密に近づくことができるかもしれない。
石倉敏明(秋田公立美術大学准教授)
[1] 秋田県立博物館編・発行『菅江真澄、記憶の形』、2018年参照。
[2] 長坂有希『これから起こるはずのことに出会うために』(会場内配布冊子)2019年、3頁。
[3] 長坂前掲書、6頁。
[4] ティム・インゴルド『ラインズ 線の文化史』(工藤晋訳)、左右社、2014年、40頁。
[5] 長坂前掲書、10頁。
[6] エマヌエーレ・コッチャ『植物の生の哲学 混合体の形而上学』(鵜崎正樹訳)、勁草書房、2019年、112頁。
[7] コッチャ前掲書、55頁。
Profile
◆プロジェクトが始動した2019年から展覧会開催までの制作の軌跡(過程)を広報紙『JOURNAL(ジャーナル)』に記録、これまでに4号を発行しました。
公式ウェブサイトではバックナンバーを公開しているほか、希望者には郵送も可能です。
これまでの関連記事は#ARTSROUTES
Information
展覧会「ARTS & ROUTES -あわいをたどる旅-」
https://www.artscenter-akita.jp/artsroutes/
■会期:2020年11月28日(土)〜2021年3月7日(日) 9:30~17:00
■会場:秋田県立近代美術館(秋田県横手市赤坂字富ケ沢62-46 秋田ふるさと村内)
■TEL:0182-33-8855
■観覧料:一般1,000円(800円)/高校生・大学生500円(400円)
※中学生以下無料
※( )内は20名以上の団体および前売の料金
※学生料金は学生証提示
※障害者手帳提示の方は半額(介添1名半額)
■前売りチケット販売所:秋田県立近代美術館・秋田ふるさと村・さきがけニュースカフェ・ローソンチケット(Lコード:21782)
・主催|ARTS & ROUTES 展実行委員会(秋田県立近代美術館・AAB秋田朝日放送)・秋田公立美術大学
・出展作家・プロジェクト|岩井成昭・迎英里子・長坂有希・藤浩志・菅江真澄プロジェクト(石倉敏明・唐澤太輔)・秋田人形道祖神プロジェクト(小松和彦・宮原葉月)
・企画監修|服部浩之
・企画運営|NPO法人アーツセンターあきた(岩根裕子・石山律・藤本悠里子・高橋ともみ)
・グラフィックデザイン|吉田勝信・梅木駿佑
・ウェブコーディング|北村洸
・後援|横手市・横手市教育委員会・秋田魁新報社・河北新報社・朝日新聞秋田総局・毎日新聞秋田支局・読売新聞秋田支局・産経新聞秋田支局・日本経済新聞社秋田支局・横手経済新聞・CNA秋田ケーブルテレビ・エフエム秋田・横手かまくらFM・エフエムゆーとぴあ・FM はなび・秋田県朝日会・東日本旅客鉄道株式会社秋田支社