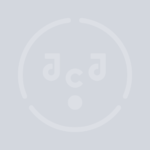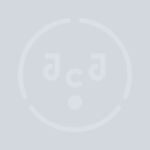自らの身体的な行為を用いて身の回りの環境との対話を試みるパフォーマンスや、環境を捉え直すことに着目したインスタレーション・アートの制作に取り組む宮本一行(秋田公立美術大学大学院複合芸術研究科博士課程在籍)の個展「雪面の歩行 Walk on the Snow Field」を、12月25日(月)まで秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINTで開催しています。
▶︎環境と身体的な対話を試みる 宮本一行個展「雪面の歩行 Walk on the Snow Field」
11月14日(火)には、自らの声や身体をプラットフォームとして、音楽、美術、舞台芸術の境界線を横断するパフォーマンスを行う山川冬樹をゲストに招き、トークイベント「身体と空間のサウンドスケープ」を開催しました。制作に込めた考えや、鑑賞者の作品との身体的な関わり方などに及んだトークの様子をお届けします。

重なる呼吸・身体のリズム
宮本:作品は体験していただけましたか?
白い木製パネルを並べた舞台が設置され、この上を鑑賞者が歩くと音(音響表現)が空間に響く仕組みになっています。舞台の下には振動スピーカーを設置しています。体重を移動させながら壁面にある写真(視覚表現)を鑑賞すると、足元の舞台の木の板がたわみ、振動スピーカーに伝わって、少しずつ空間の中に音響表現が立ち上がってきます。行為によっては音は鳴りません。そんなシンプルなインタラクションを作っています。
会場入り口のモニターには、北海道の大雪山系を歩いた記録を流しています。一定の歩行速度で雪面を歩行し続ける行為によって得られた体験を、音響表現と視覚表現で表す形で作品として構成しました。視覚表現は山を歩いたときの特徴的なシーンを8つ設置しています。
舞台の板は9枚あり、視覚表現はその周縁の板8枚に対応するように置いています。視覚表現の正面に立つと僕がその時歩いていた足音、雪の音が展示空間の中に立ち上がってくるという構成になっています。この旅はヌプントムラウシ避難小屋と呼ばれるところへのデポ(装備・食料などを一時的に保管しておくこと)でした。中央の板からは、その小屋で撮影をした川の音が流れています。


宮本:みなさんは秋田の雪を知っているので共感していただけると思いますが、雪面は一見すると歩いた時にどのような反応が雪面から返ってくるか想像しづらいです。もしかしたらすごく硬い場所があるかもしれないし、ずぼっと足がハマってしまうこともあるかもしれない。
そういった体験から、見た目はフラットな状態にし、板の上を歩くとある場所からはにぶい足音が返ってきたり、別の場所からはゆっくりしたテンポで甲高い足音が返ってきたり。見た目は同じようでも、場所ごとに個性が現れます。
山川:トークの前に展示を鑑賞しました。何をやっていたかというと踊っていた。ムーブメントを誘発させるインスタレーションだなと感じました。鑑賞者は最初、インタラクションがあることを気付かずに写真を見ます。その鑑賞する時の身体性は、身体がない状態に近いといってもいい。物理的にはあるが、身体の意識がない。
BIYONG POINTのようなホワイトキューブは真っ白な空間の中で目だけになるように強要されるような空間だと思います。そのホワイトキューブが、雪景色のイメージにつながり、足元の板にかける体重によって音が変化すると分かってくると、楽器のように鳴らしたくなってくる。
先ほど宮本さんが言ったように、雪面はどういう反応が足に返ってくるか分かりません。どのように板と関わると、どういう音の変化があるか、鑑賞者は探るわけですね。鶯張りの床みたいに唐突にキィと鳴るので、鳴らさないように、あるいは意図的に鳴らしてみたり。そうやって雪面のメタファーでもある床面と対話していくうちに、動きがダンサーみたいになってきました。
宮本さんが歩いている時のビートと言っていいようなリズムがあって、その上に自分がゆっくりと探りながら動いていく。それが単に楽器を鳴らして遊ぶという子ども心に近い楽しみ方から、だんだん探っていって、想像力が発動してきます。足のリズムだけではなく、寒い冷たい冷気が口の中から気管支を通って肺に出入りしているような体の中と外を出入りする呼吸のリズムも感じてくる。
最初はその音と関係する宮本さんのその時の身体のありようをイメージしていました。ですが、ふと写真が目に入った時、宮本さんは蓄積する筋肉の疲労や極寒の中で体温を保とうとして体を動かしてるという感覚を感じながらこの風景が見えたのかな、と伝わってきました。

宮本:この雪山の旅では、片道6時間ほとんど休憩なしに歩き続けて小屋に1泊して、帰路をまた6時間くらいかけて歩きました。リュックにGOPROを取り付けて、音は耳に付けるタイプのバイノーラルタイプのレコーダーを付け、記録を録ってはいました。けれど実は記録を振り返ってみても全く覚えていません。
写真の8つのシーンというのは、例えば沢水が流れていてちょっと一休みしたところであったり、崖を横断する前に装備を整えるために一呼吸置いたりしたところであったり、立ち止まってこれまでの山行とこれからの山行を想像し、そこから再びまた歩き出すといった時のシーンでした。映像を見返した時に、あぁこのシーンは自分の中でも深く記憶に残っていたと身体的な感覚がありました。そういう特徴的なシーンを8つ選んで、今回作品の中に展示として再表象しています。
山行は直線距離でいうと、18.5km。整備されていない雪山を開拓しながら歩いています。
展示の足音に気づいた方から「結構早い速度で歩いているんですね」というコメントをいただきました。旅ではパーティは組んでいましたが、それぞれのペースで歩いています。だから、どんどん足を出さないと見失ってしまう。そう意識しながら歩いていたので、早足でした。
そんな中でも、僕は歩く速さをテンポ140(一秒間に2歩よりも少し速い程度)にすると自分の中で決めていました。この8つのシーンは特徴的にテンポがずれたシーンでもあるんです。歩き出しだったり、歩くのをやめた時だったり。
山川:テンポ140を正確に刻める人っているのかな。ピッタリはなかなか難しいですよね。例えば心臓の音は体の状態とかでリズムが違いますからね。
宮本:心臓と呼吸の音というのは、自分が極限状態になってくると同じテンポになっていきます。その心拍数、呼吸、足跡がリンクしてくると、周りの音がすごい聞こえてくるようになりますね。ただ、その瞬間を歩いていた時は感覚的には捉えられていたものが、終わってみて記録映像を振り返っても、何も思い出すことができない。
山川:呼吸と心音がシンクロして、そして何も覚えていないということですよね。通常の状態とは違う状態になったときに、周りの音が聞こえてくるとのことですが、それは宮本さんの言葉からすると聴取にあたるのでしょうか。
宮本:難しいところです。聴取というのは音を聞き取ること。今回は一般的な音楽の聴取というところとは外れた、音を体の中に引き込む、自分の内側に捉え込んでいくような感覚を意識しています。ライブパフォーマンス中の身体感覚に近いような。演奏をしているけれども、徐々に自分だけではない、いろんな要素によって演奏していく場所の音をつくっていく。周りで音を発している人や観客に演奏させられているような感覚に近いなと思いました。
山川:よく分かります、その感じ。今の話を聞いて思い出したのは、2019年に瀬戸内国際芸術祭で発表した「海峡の歌」という作品です。国立ハンセン病療養所の「大島青松園」というところで発表しました。ハンセン病を患った人は強制的に隔離されたという歴史があり、かつては大島から海を渡って四国本土に泳いで逃げようとする人がいました。瀬戸内海は穏やかですが潮の流れが速いので、亡くなる人もいました。
その歴史を受けて、僕は四国本土から大島に泳いで渡るということをしました。泳ぐ時は自分の体のリズムを一定にキープし続ける。それが乱れると速度が落ちてしまう。怖いと思ったら筋肉がこわばって速度が落ちる恐怖を克服すると、呼吸のリズムもキープできて泳げました。周囲への意識、ゾーンに入っていくような、ミュージシャンが演奏していてもお客さんの反応を見ているとか、周りの音が聞こえるとか、その感じに近かったです。
宮本:他者とセッションする、同調していく感覚がありそうですね。
山川:この展示室では、その時宮本さんが必死で刻んできたリズムに鑑賞者が自分の時間を重ね合わせていきます。僕は踊ることでレイヤーを重ねていく面白さがありました。

身体の内側と外側の音を同時に感じとる
宮本:今回のトークテーマは空間と身体というキーワードで音の環境(サウンドスケープ)をタイトルにしました。空間と身体という言葉について、僕は空間は自分の外側のこと、身体は内側のことと分けて考えています。
今回展示の中で意識していたのは、外の音と体の中の音をどう同時に感じていくか。歩くというのは自分の身体にも振動が入ってくるし、外に向かって足音として響き渡っていく。そういう2つの側面をどのように同時に感じとっていくかを考えていきました。
山川:単純な話をすると、普段から感じていますよね。人間が耳から聞く音は骨導音と気導音があります。体に響いている音は頭蓋骨などを振動させて伝わる。でも声は耳からも空気を振動させる気導音として聞いている。録音した自分の声に違和感を覚えることはあると思いますが、それは骨導音ではない自分の声だからです。自分が声を発する時は、体の振動と外の空気の振動をミックスして聞いているということですよね。
宮本:そうですね。ただ、身の回りのいろいろな音を内側に取り入れるというのはどういうことか興味があり、今回展示の中で考えて取り組んでみました。
一般的な展示の鑑賞体験は行為的に見ていかなければならないと言われることが多いですが、どちらかというと鑑賞者としては受け取る部分が多いと感じています。観察して、アクションを仕掛けたら返ってくるリアクションに感激をしてしまうことはよくある。そう言った行為に受動と能動の関係はあるにしても、作品ありきで、作品から受け取るパワーの方が強いと感じています。
今回の展示では、鑑賞者自身が自分なりの鑑賞体験を作り出してもらいたかった。僕の作品表現ではありますが、鑑賞する人たちがそれぞれのストーリーを導き出してほしいと思いました。声を出すのと同じように、自分の音を出して、返ってくるというようなことを、作品で足元の音と自分が歩くことを連動させて体験してもらえればと考えました。

山川:自分の中に外の音を取り込むというのは、単に作家が表現として出した音から、鑑賞者が能動的に関与したことによって音に変化が生じて、鑑賞者自身が演奏した音に近くなるということですね。つながりを見い出すことが、外の音を取り込むという風に考えている。どうでしょうか。
宮本:聞き取るということに関して、受け身だけではない聞き取り方があると感じています。これまでパフォーマンスや身体表現をする表現者と鑑賞者の隔たりが生まれていると感じていました。今回の展示も実際に雪山登山をしてもらった方が、より鑑賞体験が豊かになると思うんですね。
山川:やはり雪山でのそれぞれの個人的な経験を思い出しますよね。この空間に入った時、僕自身が経験した雪の匂いの記憶が出てきました。自分の時間を過ごし、その音が聞こえる。この作品の中で聴取というのはどういう形であるんでしょうか。
宮本:まさに声を聞き取ることと一緒ですが、重力を板にかけるという部分に気付いた人が、自分の体の動きに対応して音が変化するという身体の行為と、空間に現れた音の変容を体験してもらうことが重要だと思います。
音楽でいうならライブパフォーマンスに行く人はそこの場所の熱量だったり、ベースの重低音を体で感じるというのはあると思います。一方でヘッドフォンで聴くことに慣れてしまうと、感じとれる情報がどんどん耳だけに集約してしまって、体全体のセンサーが鈍るのではないでしょうか。身体感覚と連動するような聴取体験というのがこれから重要ではないかと思って試みています。
山川:板というメディウム(媒体)も重要になりますよね。板は板でないように振る舞っているけれども、板には鶯張りのような軋みがあるし、ある種の周波数のようなフィルターのような何かが生まれるのは、板が引き起こす現象。メディウムとしての板が重要なんではないかと思い始めてきました。板は秋田プライウッドさんからの提供の秋田杉の合板ですよね。
宮本:そうですね。作品を構成していく中で、なにか想定外の音が鳴るというのは重要だと思っていました。鶯張りのような音は意図的に鳴るようにしています。以前の作品でもそれを利用したものがあります。2020年に潟上市で、建築が生きている音を自分の歩くという行為によって引き出すインスタレーションを展示しましたが、その時は幸運にもリサーチする対象や環境と展示する場所が同質だったので鑑賞者に理解してもらいやすい展示になりました。
今回難しいなと思ったのは、北海道の雪山で歩いたものを秋田で展示をしているというギャップをどういう風に受け入れられるかということ。そこで秋田杉というメディウムを中間に置ければいいなと選択した経緯があります。

世界の捉え方は人それぞれのレンズで
山川:身体とサウンドスケープという話とつながると思うのですが、ホーメイの話をさせてください。ホーメイがなぜ生まれたかは文字のない文化なので誰もわかりません。現地に行きましたが、限りなく外の環境に近い環境で住んでいた遊牧民の人たちの文化です。環境が育んできた聴力でとても耳がいい。
さらに山、森の中はすごく静かだけど騒がしいリズムがあります。気配で騒がしい。そこに普通の感覚で人間が入ると、気配を消さなければいけないという気持ちになる。「お邪魔します」というものではなく、周りの気配に配慮しながら、自分の存在をほかの動物に気づかれないように。
ホーメイってここからきたのかと思いました。自然環境の中で生きるために感覚が研ぎ澄まされて耳が良くなった。外に向かっている時は周りの環境を聞くために使うけれども、体の中に折り返されたときにホーメイが生まれた。つまり、自分自身が発する声に、外に向かっている鋭敏な聴力が向いた時に倍音を見つけた。喉の奥から聞こえるこの微かな音をどうやったらもっと強調できるかとなる。試行錯誤してみて、外に向かっていた感覚が中に折り返された時にホーメイの芸術が確立されてきたに違いないと思います。自分の身体への聴取のような。
宮本:作品を体験する人の視点に立つと、しっかりとしたプロセスがないと成立しないと思っています。鑑賞者が作品を見にいくまでにどういう経験を経ているか。聞いたことのない音を聞いて、作品の音に気付かず、音として聞こえていないという経験はあると思います。そのことに気付くきっかけを作ることも重要だと思います。表現を鑑賞者が身体にどう取り込んでもらえるのかというのも同時に考えないといけないですよね。
山川:展示場所がギャラリーでいいのかということにもなりますね。必ずそのギャラリーの空間の鳴り、響きがある。それがある以上、その響きを素材にしていかなければいけない。そこでしか体験できない音というのもある。それをもっと開いていこうとするならば必ずしもギャラリーという場所に限らないので、いろんな場所を素材として響かせてもいい。
宮本:僕はBIYONG POINTで展示するのは2回目なんです。1回目の時、かなりリサーチしましたが、空調機の音などは結構特徴的です。ここの空間はすごく反響して均質な音の反射をしないので、実は音の展示には向いていません。例えばトーク映像などをモニターで展示してしまうと何を喋っているのかわからない。すごく面白い反響をする場所なので、そういったことを意識しながら作っています。
山川:鑑賞体験の中で、空間が持っている響きが感覚に残る割合は大きいらしいです。宮本さんの作品で体感したことを自分の中で反芻するときに、この空間が持っている響きというのがかなり大きく存在することになります。だから単に見るだけでなく目以外の要素で感じる鑑賞をギャラリーという場所でやろうとすると、当然ギャラリー自体も素材になる。だからギャラリーを楽器として使うぐらいの使う必要があっただろうし、場合によっては白いカーペットみたいなもので響きを殺すこともできますね。
宮本:いろんな五感で感じとる。視覚的な作品であっても場所が持っている色々な要素から何か感じとることはすごく大事ですね。
山川:キュレーターの人がそこまで分かっていないこともある。なぜそこまでこだわっているのだろうって。そういう世界の感じ方を知っているというのはすごい大事だし、僕自身のことでいうと、ホーメイを学んだことが世界の見方そのものになっています。
みなさん、それぞれ専門的な分野を持っていると思います。一番得意、専門的な分野で使っている手法だったり、世界の見方だったり。例えばカメラマンだとしたら、世界を見る時の目がレンズになっている。それも人それぞれの違う形のレンズだと思います。
僕の場合はホーメイをやってきたので、世界の捉え方や見方もホーメイっぽい。目でも倍音を見てしまうというか。ホーメイの倍音って声の中に潜在している特定の音階だけを響かせるのだけども、パッと見ただけで見えない周波数を強調して見つける、見えにくいものに目を凝らすというか。
自分と違う世界の捉え方をしているアーティストとコラボするのは面白いですね。
宮本:僕はバストロンボーンをやっています。吹奏楽やオーケストラの中でも地味な楽器なんです。特にトロンボーンはハーモニー楽器で、そのトロンボーンのベースを担っていまして、僕が音程を乱してはいけないという認識があり、周りの音を立たせてあげなければいけないという意識が確かにある。今のお話を聞いて思いました。それが今回の展示で視覚的に表したり、環境と対話をするという形で自分の得意なところが出ているかなと思います。
山川:僕がホーメイ、宮本さんはトロンボーンということですね。

訪れたゲストからも質問が上がりました。
ゲスト:雪原を歩くと色々な音が聞こえてきます。宮本さんは全然雑念がなく、音が何も聞こえなかったのでしょうか。
宮本:もちろん、いろんな雑念が頭の中を巡りました。いいこともあるし、悪いことも。でも僕はなるべく払拭した状態で歩きたかったので、頭の中にメトロノームを置いて一定のテンポを取りながら、そのことだけで頭をいっぱいにしていました。
その時に書き起こしたりすれば記憶も残せたのかもしれませんが、それよりも自分が生きていることへの安堵感が強かったです。あそこまで辿り着けば休憩ができるとか、水の音が聞こえると水が流れているぞとか。覚えている部分は間を置いてからの歩き始めだったり、休憩ができるってところだったり、そういった雑念が生まれてきて、リズムを取っているどころではなかった状態でした。
この展示も2回目に来る人はものすごく音が聞こえるようになるそうです。何度も同じことを経験していくと新しいことに気付く。なにか環境と出合うきっかけにもなっているのかなと思います。
ゲスト2:制作の中に作為的な行為と無作為的な現象が混ぜ合わさっているように感じたのですけれど、その作為性、無作為性について意識されていることはありますか。
宮本:今回はリサーチの段階ではかなり作為的に歩いていて、記録映像をみるまでは140のテンポで絶対に歩けた、もう完璧だと思って帰ってきました。最初はその歩いた12時間くらいの音源を作品にしようとも考えていましたが、うまく歩けたところだけを使って作品化するのか、自分の想定していた結果と違う部分に着目するのかと考えたときに、僕は自分が想定していなかったところの部分がまず感覚としては面白くなりそうだと思ったので、無作為的というか、歩けていなかった8つの印象的なシーンに着目しました。
今回うまく歩けたところは作品の中に使っていません。そういう意味ではかなり意識的に想定していなかった無作為を作品に取り入れたということになります。
また、ノイズが立ち上がるだけだとかなり予定調和な空間表現になってしまうので、木がきしむ音などこちらがコントロールできない音も取り入れることによって、足元に注意を向けてもらえるんじゃないかなと思っていました。
ゲスト2:コントロールされていない音源が立ち上がる方が、鑑賞者に注意を向けさせることにつながると思ったという意味でしょうか?
宮本:展示空間に関してはスピーカーなどは隠しているので、歩いたら音が変わることなどは気付かれないかなと思っていました。歩いたことによって音がなって、木がきしむことによって、足元に目を向ける。そういう意味では不確定的になってしまうが、一つのきっかけとして、足元から音が鳴っていることに意識を向けてもらえるのかなと。計画的に設計している部分と不確定的な部分が織り交ぜながら制作しました。
山川:録音という問題はありますよね。その瞬間は無作為的でも、録音した時点でそれは不確定性はないですから。
宮本:今回はインスタレーション自体が演奏される側みたいな形と考えてまして、そこでどういうふうに音を紡いでもらえるのか、鑑賞者の人たちが演奏者の一人としてなにか気付いた人が感じとってもらえるといいというのもありますね。
山川: 空間で宮本さんの身体をイメージすることで、自分の身体の状態と重ね合わせる。ある種アンサンブルみたいな。そこがこの作品で僕が面白いと思ったところ。単にインタラクティブではなくて、雪山での身体の状態と自分の身体の状態を身体イメージで重ね合わせながらアンサンブルが生まれていくような気がします。僕の感想としてはそれかな。

作品撮影:船山哲郎
Profile 作家プロフィール

宮本一行 Kazuyuki Miyamoto
1987年千葉県生まれ。2024年秋田公立美術大学複合芸術研究科博士課程修了。博士(美術)。
サウンドスケープを軸に、音と身体、環境の関係を再考する芸術実践を展開。観測者として音を聴くだけでなく、自らの行為を通じて環境と対話的な関係を探求している。近年では、身体の動作やリズムを基盤とする作曲的アプローチや、他者の身体感覚に接続するワークショップに取り組んでいる。
Profile ゲストプロフィール
Information
宮本一行 個展「雪面の歩行 Walk on the Snow Field」
▼ 宮本一行 個展「雪面の歩行 Walk on the Snow Field」DM(PDF)
■会期:2023年9月16日(土)〜2023年12月25日(月)
入場無料、無休
■会場:秋田公立美術大学ギャラリーBIYONG POINT
(秋田市八橋南1-1-3 CNA秋田ケーブルテレビ社屋内)
■時間:9:00〜17:30
■主催:秋田公立美術大学
■協力:CNA秋田ケーブルテレビ、秋田プライウッド株式会社
■制作協力:NPO法人アーツセンターあきた
■お問い合わせ:NPO法人アーツセンターあきた
TEL.018-888-8137 E-mail bp@artscenter-akita.jp