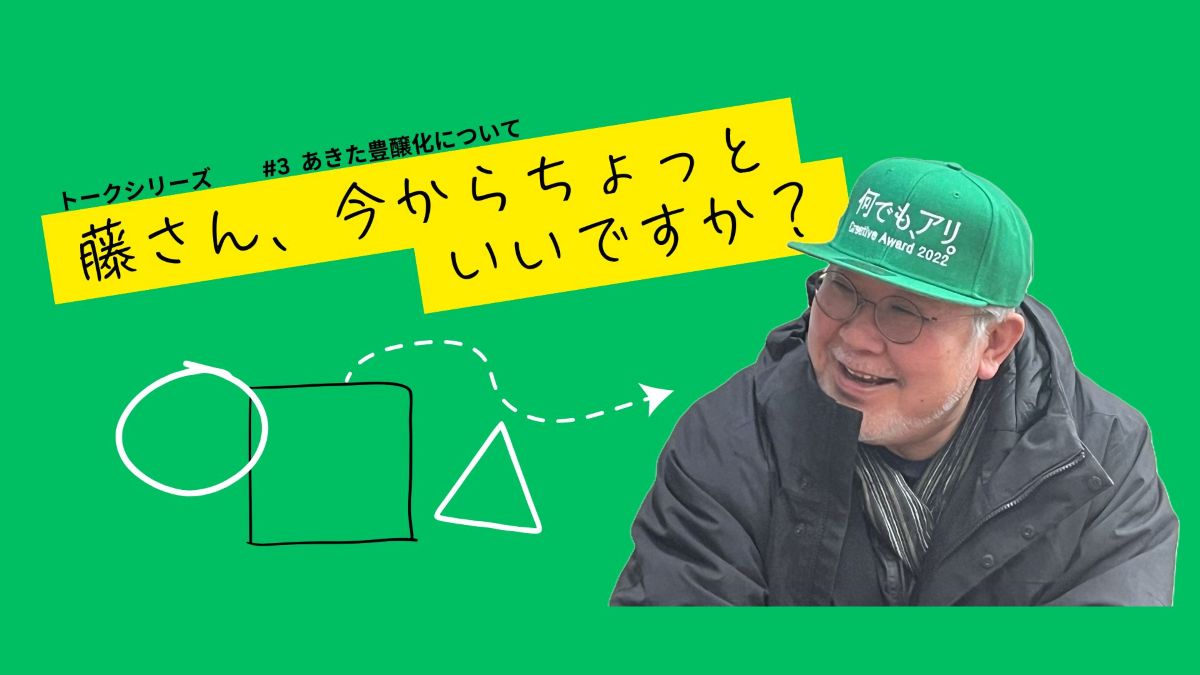アーツセンターあきたの理事長・藤浩志と、事務局長の三富が、アーツセンターあきたのことを中心に四方山話を繰り広げる不定期のトークシリーズ「藤さん、今からちょっといいですか?」。収録方法を毎回実験しつつ、三富が勝手にテーマを設定し、藤に問いを投げかけるスタイルで進行します。
第3回目は「あきた豊醸化」をテーマに、「豊かになる」ことの今日的解釈について、秋田公立美術大学から秋田県立近代美術館への移動の車中で伺いました。
※映像中の音声は、車の走行音等の雑音が少しはいっております。ご了承ください。
活性化ではなくて、豊醸化
三富
いきなり今日のテーマですけど、「あきた豊醸化」。テーマをご案内するメールにも書きましたが、豊かになるっていうことの価値観が変わってきている。
藤
そうだよね。
三富
それなのに、例えば自治体の動きを見ると、まだ人口を増やすという方針をとりつづけていて、それが果たして現実的なのかとも思って。改めて藤さんに豊醸化の意味とか、災害が多発し、気候が変動し、人々のマインドが変わってきている中で、どう豊かさというものを定義して、豊かになっていくためにどんなアプローチをとっていくのか、お伺いできればと思っています。
藤
豊醸化と言いはじめたのは、活性化という言葉への違和感がきっかけになっています。
三富
2007年ぐらいの藤さんのブログに、そのように書かれてました。
藤
活性化に対する違和感は、もっと前からもっていて、恐らく92年頃に都市計画事務所に勤務していたときから。活発になるのはいいんだけど、一つの言葉で全部の地域が全く同じ価値観で変わってゆくことに違和感があった。活性化する地域があってもいいんだけれど、なんかもっとじわっと、ゆっくり、別の展開をしていく様を表現する言葉を探していた時に、思いついたのが「豊醸化」。一般的に用いる「豊穣化」ではなくて、《醸す》という字をあてた造語。醸すといえば、最近「創造性酵母菌」というキーワードが糸島の活動の中からでてきたりしているけれど、地域の中で、活動が連鎖したり、循環したり、そんなことが重要ではないかなって気がしたんですよね。
もう一つ前提として、文化芸術は豊かさのためにあるものではないということ。あくまでも生きるためにあり、生き延びるためにあると思っている。豊かさについて、誤解というか、そう思うように圧力を受けてきたというイメージをもっている。例えば、その時々の豊かさの定義を考えると、ある種の貧しい状態から、物が増えたり、食料が増えたり、生活が違う形に変化してったりするときに、豊かさの象徴としてのイメージが輸入されたり、持ち込まれてくる。アメリカの生活とか、フランスの生活とか。それに対する違和感もすごくあった。だから僕は途上国へ視線をもっていったし、もっと原初的な生活の方がある意味豊だったんじゃないかと考えていた。今だったら、そういう考え方は当たり前にあるじゃない。何もない自然の中での生活の方が、ある意味時間的には豊かであるという考え方とか。そういった価値観の変化みたいなものを1980年代のバブルに向かう社会の中で、感じてたのかもしれない。
豊醸化という言葉の中で、可能性を感じるのは「醸す」という部分。醸すというのは、面白い状態で新しいものに変化していくということを表す言葉としてイメージして用いています。12年くらい前に、東京のArts Initiative Tokyo(AIT)がいろんな人に東京のイメージについてインタビューをしていたことがあって、僕も取材を受けたんだけど、ちょうど豊醸化のイメージの延長で、「東京は水栽培の街」と答えていた。
土の人とか、水の人とか、風の人という例え話を良くしているけれど、水というのは、僕には、興味と関心を象徴するイメージなのね。土のイメージは、土地。作物をつくったり、その土地から芽吹いて花開かせるというのが土の役割。そこに種があっても、土地が豊かじゃないと、何も育たない。そこに水が注がれて、光が当たり、種が芽吹いていく。光は、ジャーナリストとかメディアだったりを象徴するイメージ。光が当たると、風の人が別の土地に運んでいく。そんなことを考えていくなかでちょっと気づいたことがある。
光をあてたり、風で運んだりというのは、どちらかというと立場や仕事としてやっている人が多い。ポイントとなるのは水の人で、興味・関心を注ぐ人。これは利害関係なく、消費に近い立場で、応援したり、推し活したり。そこには需要と供給のバランスがあるのではと思い始めて、東京は関心のある人が集まって、圧倒的に少ない土の量に対して、エンタメとかさまざまに育まれる様が水栽培だなって思うようになったんだよね。一方で、秋田は、土地が豊富にあるよね。
さらに考えてみると、水と土のミックスの泥の人とか、光と水のミックスで虹の人とか、風と土だと土埃で嫌だなとか、物事はもっと複雑だからいろいろな要素が絡んでいる。人の属性は明確にわかれるものでもないから、いろんな立場の人が様々に関わっていくし、それによって生み出される状況も変わる。だから、生態系とか豊醸化といったときに、最終的には状況をどうつくっていくのかが重要になってくるのかなって。僕は研究者でもない、単なるしがないアーティストの妄想みたいな、何の根拠もなく勝手に思ってるだけの話なんだけどさ。

立場とハニワ
藤
その中でずっと気にしているのが、ハニワなんだよね。さっきも立場っていう話をしたけど、《いきる》って言ったときに、「生きる」と「活きる」の二種類の漢字がある。活きる、活動は、興味関心を注ぐ行為。生命活動の生きることも、興味関心を注ぐ活動も、個人だけではなく、立場や社会的な組織や法人との関係性やバランスが常に絡んでいると感じている。
アーツセンターあきたもそうだけれど、組織化すると、そこにミッションなり、何かの方向性をつくらなくてはいけなくなってしまう。でも個人にとっての興味関心を注ぐ活動は、どんな人であれ束縛や阻害をうけずに活動ができるということが許されていなくてはならないんじゃないか。それが剥奪されると苦しくなるわけだけど、それを提供しているのが個人ではなくて、法人で、僕にとってはハニワじゃないかなという思いになってきて。その関係って、難しいなって気がするんですよね。
興味関心を提供しているのも実はハニワさんで、本にしても出版社が絡んでいるし、作品もギャラリーとか業界が絡んでいたり、個人の思いや表現が起動したり、社会化されたりするには何かシステムがかならず介在する。そうすると距離の取り方が難しくて、動きにくく感じたりもする。三富さんが日頃悩んでるあたりもその辺かなと思うよね。
三富
そうですね。
藤
だから法人として、秋田の豊醸化っていったときの言葉には、ハニワさんの言葉でしかないのかもしれない。けれど本当は、個人の、秋田の人たちがいかに楽しく暮らしていける状況になるかっていうことが重要で、それは一人ひとりの問題であって、そこに法人と個人の関係をどうつくっていくのかというのを意識したりするけれど、僕自身も個人の活動よりは、立場の活動をどちらかというと優先してしまうことになっている。
何より個人だと消費するだけになっちゃうよね。 生産することが個人の興味でどんどんできたらいいんだけれど、どうしても大学の研究になったりとか、美術作家っていう立場の一つになってしまう。
三富
立場を拠り所としながら、時に言い訳にもつかっているんですかね。
藤
逆にいうと、ハニワさんも悪者ではなくて、あり方かなっていう気もする。だから、秋田市がどうあるのかとか、秋田県がどうなるのか、うちの大学はどうあるのかとか、アーツセンターがどうあるのかって言ってるのっていうのは、全部ハニワさんというか、組織の問題。秋田の豊醸化っていった時に、漠然とした秋田という団体がどういう形になっていくのかなと思うよね。でもその団体を構成してるのは個人なので、団体を頼りに個人が大切で面白い活動ができる状態になることが大切だと思うわけ。それにはまる人もいれば、逆にそこに苦しむ人もいる。あんまり苦しまないようにするにはどうすればいいか。秋田が人口減でどうしようというとき、それは秋田という団体で考えると、税金が減って大変だけど、個人で考えてみると、一人でのびのびと使える土地が広くなるし、可能性が広がるなって思えたりもする。
秋田の中の100のグリッド
藤
僕が関心をもっているのは、閉じた環境について。最近はインフラの在り方みたいなものがすごく問題になってきているよね。今高速道路を走っているけど、自治体的に考えると、これをつくって維持するお金がなくなっていくという課題がある。あと、排水とかエネルギーも問題になっている。それを踏まえたときに、実は一つのグリッドの中で生活できるんじゃないかと思っていて。これまでは、全部それを連結して一挙に処理しようとして、巨大な送電線と発電施設や排水設備を整備してきた。移動も高速化してきたけれど、デジタル社会の次の状態を想像すると、そんなに早く移動することが良い生活につながるのかなと思ったりもする。ライフスタイルが変わっていくことが想像できるし、今も既に都市よりも地方で生活するメリットも徐々に注目を集めるようになってきている。最初に話したように、豊かな自然があって、食糧が採れて、薬草があって、地下水があるような生活。そういった生活を集落単位で営んでみて、秋田の中に100箇所くらい、もしくは500箇所のグリッドをつくっていって、そのエリア内で循環する。グリッドの中は完全に閉じる必要はなくて、緩やかにつながっていて、外からも人が入ってきて交流があって、いろんな体験ができて。例えば、五城目町でやっているシェアヴィレッジのように、昔ながらの生活を体験しながら、生きる力を取り戻し、育んでいくということが、一つの豊かさみたいになっていくのではないかな。

最近、中学生がその地域に一番根づいているよねっていう話をNPO法人プラス・アーツの会議でしていたことがある。小学生よりも体力があるし、私立中学に進学して校区外に出る子もいるけど、多くはその地域の学校に通っているから、災害が起こった時に高齢者とか、障がい者とか、動けない人たちを救い出せる力をもっているのが中学生で、防災教育の中心になるんじゃないかという話。そして、これからの防災や、災害が起こった後の暮らしを考えたときに必要なのが、どうやって食糧や水を確保し、排泄物を処理するかということ。古い集落で各々にやってきたことが、未来の集落をつくっていくことにつながるんじゃないかって。そうなると中学校の教育の中に野草について学ぶ機会があっても良いんじゃないかと思ったりする。昔は小学校の中に必ず野草園があったという話を聞いたことがあるけれど、昔はそうやって、ケガをしたとき、熱がでたとき、咳がでたときにつかう野草を皆が知っていて、地域に病院がなくても、薬局がなくても、自分たちで生きていくための知恵をちゃんともっていたんですよね。それが分業化されて、病気になったら、怪我をしたら、病院に行くという暮らしに変化していった。それでも緊急事態の時には、畑を耕し、農作物を育て、最近は熊の出没が話題だけれども、熊をとって食べるみたいな発想の転換ができることが重要。そして、生活に必要なものを、目の前にあるものでつくっていくこと。それが生活の中の面白さになっていったり、豊かさにつながっていく。何かあったときに、何かを消費しようとするんじゃなくて、何かをつくり出そうとする。どうにかしようとする態度を持つ人、どんどんつくることの連鎖を引き起こす人がいることで、その地域は全然変わっていくと思う。それが、豊醸化といったときの一つの方向性としてあるね。
三富
話を聞いていての感想ですけど、私が思っているのは、今の社会の中心にいらっしゃる方々は、経済成長を遂げて、バブルを経験して、あのときは良かったっていうところに戻そうというイメージを持っているのを感じて、それに対する違和感なんだなと。
藤
僕も違和感だらけ。戦後の経済復興っていうのは同じ方法では繰り返すこと何でできるわけがない。一方で、長い歴史の中でみると、ずっと繰り返されてきたことだとも思うんだよね。人間というのは常に破壊され、再興し、また破壊され、再興を繰り返す。振り出しに戻すみたいな感じなのかな。よく33年周期の話をするけれども、人ってそういうもんなのかなと思って。自分たちが学んできた生まれてからの33年間と、33歳から65歳までの活動期と、それを振り返って次につなぐという66歳からの33年毎の周期があるとして、人はその周期の範囲しか知らないわけで、未来はわからないもの。今の若い人たちの感覚・感受性を、僕らもある意味わからないし、わかるわけがない。
三富
わかりたいんですけどね・・・
藤
委ねていくしかないし、わからないっていうことをわかったほうがよい。物事の価値は状況によって変わるから、何が大事かというのは自ずと変化していく。車社会になってきたから、道路が整備されているけれど、これも将来変わっていく可能性があるということだよね。
「民具ラボ」から見えてくること
藤
今「民具とアートとアーカイブの研究所(民具ラボ)」をやっているけれど、油谷さんが集めた物をみていくと、それぞれの時代の価値観というのは、物に残されていることからわかってくるよね。物だけではなくて、新聞とか雑誌とか、ノートとか、テキストがいっぱい残っているのも面白いよね。時代を反映しているのと、文字が一番残った時代であるというのを感じる。昭和・平成は、印刷技術が発達して量産が進んだ時代で、市民がテキストを書き残すようになっていった時代。2000年以降、デジタルが出てきてから、自分で書くことが少なくなっていくし、デジタルだと消えてしまう。もしかしたら文字はこれから先あまりモノとして残らないかもしれないよね。
江戸時代や、それ以前だと、権力者が文字を残してきたから、力のある人たちの価値観と考え方しか残っていない。一方で、油谷さんのコレクションの中にあるのは庶民の生活の中にある多くの文字情報。

三富
今回の分類整理では、商店の領収書とか発注書が沢山でてきましたよね。
藤
デジタル決済になったり、DX化が進むと、残らないよね。データも廃棄されるようになるし。そういう時代の変化、価値観の変化を見ていくと、明らかに世代で確実に価値観が変わっているし、30年単位で使う言葉も変化しているというのがわかる。
三富
藤さんがいうグリッドの中でコミュニティを形成してサバイバルするという発想は、これからの世代には共感しやすい発想かもしれないですね。そういうライフスタイルの事例がすでにあって、興味を示す人が増えていることや、比較的閉じた中でのコミュニケーションに居心地の良さを覚える価値観が定着している側面を考えると。
藤
関心をもつ人は多いだろうね。
最近デジタル化することの意味や必要性について質問を受けたことがあって、「アクセスをつくるために必要」ということをとっさに答えたんだよね。美術館や博物館の収蔵品をデジタルアーカイブすることが増えているけれど、作品はやっぱり体験が重要だから、デジタル化した作品は体験を担保できるのかという問いがでるよね。でも、デジタル化されるから、アクセスしやすくなるし、アクセスすると、やっぱり実物を見に行きたいという意欲が掻き立てられる。実際の体験につなぐアクセスをつくるのがデジタル化の役割。それでさっきの話に戻ると、今は、デジタル上でいろんな体験をできるようになっていて、一見その体験の向うにある実体験の必要性は薄いと捉われがちだけれども、土をいじって作物ができるとか、弓矢でイノシシを仕留めて解体するとかっていう作業の記憶が、何十世代も何百世代も前から遺伝子には組み込まれているんだよね。だから実体験に接することで血が騒ぐっていうことがあるんだと思う。実体験にはデジタル化できない現在の人類にとっての未知の知恵が無限にある。デジタルで出会うことによって、遺伝子の記憶が、何かをやってみたいと導き体験してしまう。そうするとはまるんだと思う。人間の体の体験することに対する欲求っていうのは、潜在的にあると思うんだよね。
例えば井戸水をくみ上げて、お湯を沸かしてコーヒーを入れて飲むと、本当に美味しいんだよね。それを知っているというのは、豊かなことだと思う。自分で焙煎したコーヒー、自分でつくった米の美味しさ。あとは仲間と、親しい人たちとつくって一緒に食べる喜びは、映像やゲームの世界では見ているけれど、実際には知らない。そういう意味で、デジタルが広がれば広がるほど実体験を求めるというのはあるんだと思う。
三富
そうだとは思うんですけれど、アルゴリズムによって、多様なデジタル情報への接続が抑制されているのが現状で、その壁を突破できるんだろうかとは思いますけど。
藤
アルゴリズム自体も、経験が重なっていくと、こっちの方が人間にとって重要だと判断するようになったり、そういったものに出会えるようになっていくんじゃないかな。今はすごく偏ったものしか出てこないけれど、そういったところを操作しデザインするデザイナーが出てくるかもしれないね。
また立場の話に戻るけれど、楽観的に考えると、貨幣経済の前提ではない価値観じゃないものを商品化する人がでてきたりする可能性もある。既存の商品やサービスが飽きられて、違うものを求める人がいる限りは、そういうものをつくる人が出てきて、それが流通し始めるようになる。そうやって巡っていくんじゃないかな。
例えば、山形のスイデンテラスとか、新しい形の農業法人ができたりとか。新しいビジネスとして先駆的に注目されて成功していけば、そういう取組みに注目する人も増えていく。その意味では、秋田は既にグリッドが小さい単位で存在せざるを得ない状況になっているから、大都市型を目指すのではなくて、グリッド型を実験してみた方が面白い展開になるんじゃないかな。昔のまちづくりとか、活性化の枠組みでは、お客さんを増やすために、どこにもでもあるような流行りの商品やサービスを提供して、消費を促して、しばらくすると飽きられる。そうではなくて、過酷な状況の中でも、ここから作っていくことの面白さがあるし、僕自身も秋田で何かできそうと興味をもって来たというのがある。何もなかったっていう言い方をすると秋田県に対して失礼だけど、そこに美大ができたというのが重要な政策だったと思う。これはつくる人を集める政策だからね。
これまでの秋田、これからの秋田
三富
秋田は変わったと思いますか。
藤
秋田にいると面白い人たちと出会うよね。もちろん元々住んでいる人たちは面白い人に出会って来たんだろうけど。いっぱい面白い人たちが秋田に来ているよね。「あ、来てたんだ」ということも多いけれど、このぐらい情報が届く規模感でいいなと思う。大都市だと、いつも誰かが絶対にいるけれど、そこに対して自分がアクセスしにいかないとならないし、そうすると大変。忙しくてつくる暇がない。東京にいるときは、そういう感覚だった。展覧会も多いし、トークイベントも多いし、関心があるものもあるんだけど、自分がつくる時間を全然確保できないのと、自分が作ってるものがしょぼく見えてきて、なんかつまんないことやってるという感覚に陥る。
三富
東京は、日本の最先端で、世界で戦うレベルにあって、いろんな人たちが集まってきてるから秋田の感覚とは違いますよね。
藤
動かしている量が多いしね。 でもそれが幸せかって問われると、そうでもないという人もいることは、皆ドラマとか映画の中で表現される世界を見て知っているわけだよ。もっと違う関係の中で、つくっていく時間や体験が大切なこともね。
三富
今若い人に対して秋田にとどまる、秋田の外に出ないような施策もあったりしますけれど、そこに対しては柔軟であることを許容できると良いのかなと思いました。
藤
縛り付けるところ、束縛してくるところには面白い活動を作ろうとしている人は集まってこないよね。これまでにないようなことができそうなところに面白い人が集まってきて、その面白い人を目指して人が集まってくる。そして圧倒的に面白い独特の小さなコミュニティがポコポコできてきて、それが緩やかなつながりながら広がってゆく。そんな感じが許されるところになればいいよね。
収録方法の実験記録
●収録方法:
・前回同様に移動中の車内のダッシュボードに携帯電話を置いて録画。
・前回と同じ格安のピンマイクを用いて録音。
●成果:
・前回の反省をいかして、画角を調整してカメラをセットしたので日差しの影響を受けることがなかった。
●課題:
・今回の車は走行音がうるさく、車で撮影する際には車を選ぶ。