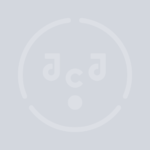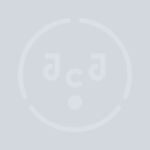秋田市在住のコレクター 油谷満夫さん(90歳)が収集する50万点を超える膨大な民具等の1000分の1程度を倉庫から取り出し、アーティストや市民ボランティアによる分類整理と、多様な分野の専門家らとともに価値を検証するプロジェクト「1/1000油谷コレクション」の一環として、モノを残すことの価値を問うアーカイブ研究会を開催します。
高齢化や人口減少の進展とともに、モノのアーカイブそのものが困難になっています。
私たちはなぜ残すのか。そして、何を、どうやって、どこに残していくことができるのか。公と民、リアルとデジタルなど、さまざまな境界や領域を横断してアーカイブにかかわる取組みを実践する専門家とともに、これからのアーカイブの可能性について議論します。
モノを残すことの価値を問うアーカイブ研究会
日時:2025年1月25日(土)13:30~17:00(受付開始13:00)
会場:秋田市文化創造館2FスタジオA1(秋田県秋田市千秋明徳町3-16)
※入場無料、要事前予約
■ プログラム
13:30-13:40 主催者等あいさつ
13:40-14:25 基調講演「民具を残すことについて」
・神野善治(武蔵野美術大学名誉教授、日本民具学会会長)
14:25-15:25 事例報告
・佐藤知久(京都市立芸術大学芸術資源研究センター 専任研究員/教授)
・施井泰平(現代美術家、スタートバーン株式会社 代表取締役)
・寺田鮎美(東京大学総合研究博物館インターメディアテク寄附研究部門 特任准教授)
・西村環希(株式会社Planet Labs PlanetDAO Founder)
<休憩10分>
15:35-16:45 ディスカッション
・モデレーター 服部浩之
(キュレーター、東京藝術大学大学院 准教授、国際芸術センター青森(ACAC) 館長)
16:45-17:00 閉会あいさつ
■ 登壇者プロフィール

神野 善治 Yoshiharu Kamino
『人形道祖神 境界神の原像』(白水社 1996)で「第37回柳田國男賞」受賞。主な著書に『くらしの造形 手のかたち・手のちから』武蔵野美術大学出版局 2019年、『木霊論 家・船・橋の民俗』白水社 2000年ほか多数。

佐藤 知久 Tomohisa Sato
1967年生まれ。京都大学文学部哲学科(哲学専攻)卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。京都文教大学人間学部文化人類学科専任講師、同総合社会学部総合社会学科准教授等を経て、2017年度より現職。日本文化人類学会会員。

施井 泰平 Taihei Shii
多摩美術大学卒業後「インターネットの時代のアート」をテーマに美術制作を開始。2014年、東京大学大学院在学中にスタートバーン株式会社を起業し、アート作品の信頼性担保と価値継承を支えるインフラを提供。
現在はTokyo Art Beatの代表、東京大学生産技術研究所リサーチフェローを兼任。主な著書に平凡社新書『新しいアートのかたち NFTアートは何を変えるか』がある。

寺田 鮎美 Ayumi Terada
専門は芸術学・博物館学。東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了、政策研究大学大学院博士課程修了、博士(文化政策研究)。大学博物館のコレクション活用、空間・展示デザイン、用者コミュニケーション等に関する新たな博物館モデルを提案し、多くの人が文化や学術知を享受し、さらにそれを創造活動につなげていくことに貢献する研究を目指している。

西村 環希 Tamaki Nishimura
大学在学時より株式会社ガイアックスにて訪日旅行者向けツアーガイドのプラットフォームの運営やイベントショー事業の責任者を担う。2022年よりクリプトに将来性を感じ、web3特化シェアオフィス「CryptoBase」をオープン。2024年、日本初の株式会社型DAOによる歴史的建造物への小口投資プロジェクト「PlanetDAO」を創業。
https://planetdao.world/

服部 浩之 Hiroyuki Hattori
1978年愛知県生まれ。建築を学んだのちに、アートセンターなど様々な現場でアーティストの創作の場をつくり、ひらく活動に携わる。アジアの同時代の表現活動を研究し、多様な表現者との協働を軸にしたプロジェクトを展開。主な企画に、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」。「200年をたがやす」全体監修。
■ 主催者等プロフィール

國政 サトシ Satoshi Kunimasa
1986年大阪生まれ。秋田市市在住。京都精華大学デザイン科テキスタイルデザイン卒業。2012年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻染織修了。2019年ポズナン芸術大学(ポーランド)短期留学。
現代の工業製品を素材に、染めや、編みといった工芸・手芸である既知の技術を使い、立体作品や建物全体の構造を利用したインスタレーションに展開。普段よく見る日用品が一変し、違う素材へと変化することに着目し、一貫して結束バンドを使った制作を続けてている。また、美術とその周辺を独自に編集・デザインし出版する「AT PAPER.」の代表としても活動している。https://satoshikunimasa.com/

藤 浩志 Hiroshi Fuji
鹿児島生まれ。京都市立芸術大学大学院美術研究科修了、パプアニューギニア国立芸術学校講師、都市計画事務所勤務を経てジャンルにこだわらないプロジェクト型の美術表現を実践。2012年より東北に拠点を移し十和田市現代美術館館長を経て現職。主な作品:「ヤセ犬の散歩」「お米のカエル物語」「Vinyl Plastics Connection」「Kaekko」「藤島八十郎をつくる」「Jurassic Plastic」等 https://www.fujistudio.co

高橋 卓久真 Takuma Takahashi
コンピュータをベースとした視聴覚メディアの開発を背景に、ゲーム、インスタレーション、ライブパフォーマンスなど、作品制作を主体とした研究を行う。テクノロジーに対して中立的な立場から、技術との共生に基づくケーススタディを通じて、表現理論の構築とその実践方法を模索している。
■ お申込み
Googleフォームまたは以下に記載のメール・電話のいずれかにより、①お名前、②参加人数、③ご連絡先をお知らせください。
・Googleフォーム:https://forms.gle/XRiPu8EMnhqkTyap7
・メール:program@artscenter-akita.jp
・電話:018-888-8137(平日9:00~17:00)
■ 会場アクセス
以下のリンクをご参照ください。
https://akitacc.jp/access
■ お問い合わせ
NPO法人アーツセンターあきた
TEL:018-888-8137
E-mail:program@arts-center-akita
Information
モノを残すことの価値を問うアーカイブ研究会
さまざまな境界や領域を横断してアーカイブにかかわる取組みを実践する専門家とともに、これからのアーカイブの可能性について議論する研究会。
プロジェクト「1/1000油谷コレクション」関連の特別シンポジウムとして開催。
●日時:2025年1月25日(土)13:30~17:00(受付開始13:00)
●会場:秋田市文化創造館2FスタジオA1(秋田市千秋明徳町3-16)
●主催:秋田公立美術大学有志(國政サトシ、藤浩志、高橋卓久真)、NPO法人アーツセンターあきた
●助成:公益財団法人小笠原敏晶記念財団 交流助成